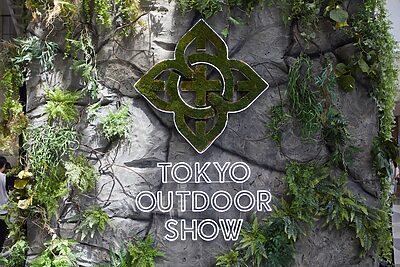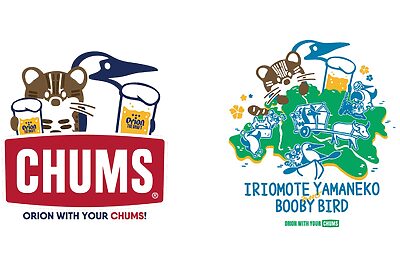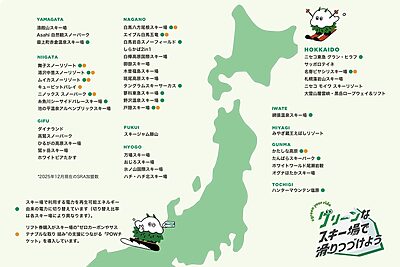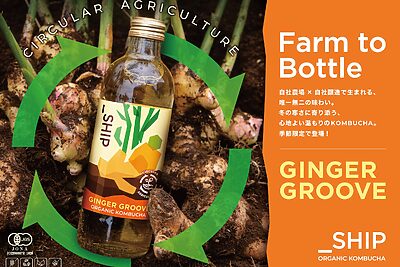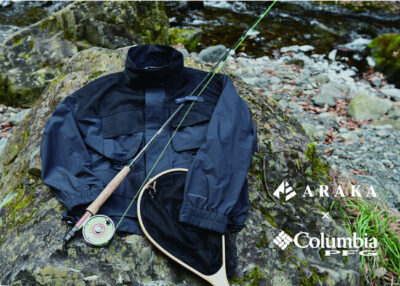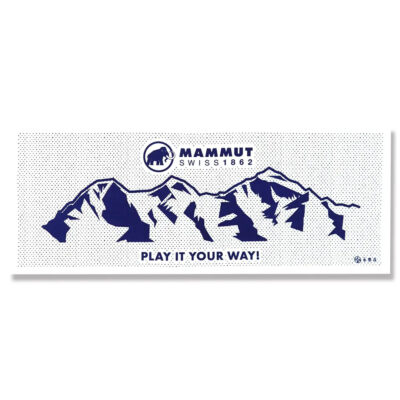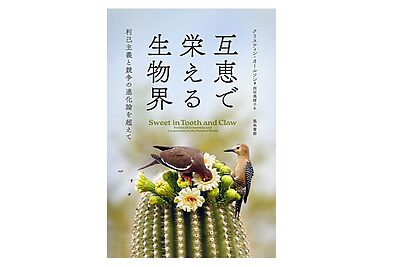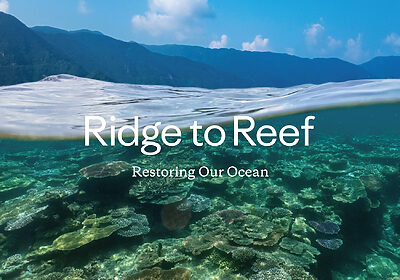サステナブルなファッションとは?

サステナブルなファッションとは、衣類の生産・販売・廃棄の過程で、地球環境や労働者に配慮したファッションのことです。
ファッション産業は、環境への負荷が大きいとされています。原料の調達から製造までに、服1着あたり約25.5kgのCO2を排出し、約2,300Lの水を消費。国連貿易開発会議(UNCTAD)では、「世界で第2位の汚染産業」ともいわれるほどです。
そのため、環境に配慮した商品づくりが求められています。たとえば、生産工程で水やエネルギーの使用量を減らしたり、リサイクル素材をつかったりするなどです。
加えて、流行を取り入れた低価格のファッション製品が増え、商品のライフサイクルが短くなっているのも問題。廃棄されたファッション製品はゴミ問題へとつながります。また、生産過程での労働環境やアニマルウェルフェア(動物福祉)などについても、考慮する必要があるでしょう。
こうした課題を抱えるファッション業界では、多くの企業がサステナブルファッションへの取り組みをはじめています。
出典:
環境省「サステナブルファッション」
大和総研「なぜ今、サステナブルファッションが望まれるのか」
サステナブルファッションへのアウトドアブランドの取り組み

サステナブルな商品づくりを目指して、多くのアウトドアブランドもさまざまな取り組みをはじめています。代表的な取り組みをご紹介しましょう。
長く着られる商品づくり
アウトドアブランドのなかには、長く着られる商品を企画し、丁寧な生産を行おうとしているところがあります。廃棄量を増やさないためです。低価格にするために商品の質を下げると、購入から廃棄までの時間が短くなってしまいますよね。
サイズ調整や修理のサービスを提供して、ひとつの商品を長くつかってもらう工夫もみられます。
リユースの促進
リユース(再使用)は、過剰な生産の抑制につながります。アウトドアブランドのリユースの例としては、企業が使用済みの衣服を回収し、まだ着られるものを中古市場で再販するなどがありますよ。消費者にもメリットがあり、新しい服より安い価格で購入できます。
古着ショップはこれまでもありました。しかし、グローバルな規模で循環型社会が目指されているなか、リユースはメーカーでもはじめられつつあるのです。
適正な在庫管理
受注生産やアウトレットでの販売をとおして、適切な在庫管理を行うブランドが増えています。必要以上に生産すれば、生産・販売・廃棄の過程で環境への負荷が大きくなりますよね。在庫管理を徹底すると、こうした環境問題に貢献できるでしょう。
素材や生産過程の可視化
素材や生産過程への配慮が商品に明示されていると、消費者にとっては安心感があるのではないでしょうか。環境や労働者に配慮した製品づくりは、商品に付加価値を与えます。また、リサイクル素材の利用などを企業が公開すれば、ブランドのイメージアップにもなりますね。
資源としての再活用
アウトドアブランドでも、資源の有効活用への取り組みが注目されています。「アップサイクル」という動きで、廃棄されるものに新たな価値をもたせることです。
アップサイクルで商品に新しいアイデアやデザイン性が加えられれば、それを手に取る人だけでなく、地球にとってもうれしいこととなります。
サステナブルファッションの海外アウトドアブランド16選

サステナブルファッションを展開している海外のアウトドアブランドを4つご紹介します。商品を購入するとき、ひとつのポイントとして注目してみてください。
Patagonia(パタゴニア)|アメリカ
「故郷である地球を救うためにビジネスを営む」を理念とする、アメリカのアウトドアブランドです。環境や社会的な課題に配慮しながら、さまざまなアウトドア・アクティビティに対応する商品を展開しています。
売り上げの1%を自然環境の保護に活用
1985年から、売り上げの1%をアメリカ内外の環境保護団体に寄付。累計の寄付金額は、1億4000万ドル以上にのぼります。
創設者のイヴォン・シュイナードは、2002年に非営利団体「1% for the Planet」を設立しました。この団体に加盟している他ブランドも、同様に売り上げの1%を寄付しています。
フェアトレード商品の販売
2014年から、フェアトレード認証された商品を積極的に使用しています。フェアトレードとは「公正な貿易・取り引き」を意味し、途上国の生産者の生活を支援するための取り組みです。
パタゴニアは自社で工場をもっていないため、労働者の賃金を直接管理できません。そこで、フェアトレードの認証ラベルがついた製品1点ごとに、工場の労働者に賞与を提供しています。この取り組みで、これまで7万2000人以上の労働者に間接的な賃上げを行っていますよ。
THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)|アメリカ
1966年に創業した、アメリカのアウトドアブランドです。多岐にわたる商品を展開し、タウンユースも可能なファッション性を兼ね備えているものが多くあります。
ロングライフな商品設計
商品の機能性や目的に合った素材を選び、長く使用できるような設計がすすんでいます。「購入した商品を長く大切につかってもらうことが、究極のエコ」という考えにもとづいていますよ。購入後のリペアサービスがあるのもうれしいポイントですね。
タグやカタログも素材に配慮
再生紙など環境に配慮した素材をつかい、商品のタグやカタログを作成しています。紙の使用は森林資源に影響をおよぼしますよね。商品につかわれている素材だけでなく、細かなところまでもサステナブルな取り組みを行っています。
以下の記事でも、THE NORTH FACEのサステナブルな商品を紹介しているので、参考にしてみてください。
THE NORTH FACEから「ACTIVE TRAIL COLLECTION」を発売
Columbia(コロンビア)|アメリカ
アメリカのオレゴン州生まれのアウトドアブランドです。日本国内では独自の取り組み「エコロンビア」を展開。アウトドアフィールドだけでなく、地域社会や自然環境にもかかわるプロジェクトを実践しています。
衣類のリサイクル
アメリカの店舗では不要になった衣服や靴を回収しています。回収した製品は繊維の処理施設に送って分類。まだ着られるものは中古として再販し、着られないものは、新しい製品の繊維に活用していますよ。廃棄される衣料を減らし、資源の保全やCO2削減に役立っています。
女性社員のサポート
女性の地位向上に向けて、健康の改善についてなど、さまざまなトレーニングを実施。男女平等を促進するため、女性に対する暴力の問題にも取り組んでいます。
トレーニングはすべての従業員に開放され、参加は無料です。女性だけでなく、男性従業員の参加も推奨されています。
MAMMUT(マムート)|スイス
1862年にスイスで設立。160年以上の歴史をもつ老舗アウトドアブランドです。もともとはクライミング用品のブランドでしたが、現在では幅広いアウトドア商品を展開しています。
動物福祉への貢献
動物福祉に積極的に貢献しています。たとえば、ダウン製品では、生きている鳥や強制的な食事で飼育されている鳥の羽毛を使用していません。第三者の認証機関により、羽毛の生産者を監査。すべてのダウン製品で、羽毛の産地や生産者を追跡できるようになっています。
ウールや革素材も、適切な扱いで生産された原料を使用しているのが特徴です。
リサイクル素材を活用
環境への負荷が少ないリサイクル素材を活用しています。ペットボトルなどの資源を再利用することで、純資源から生産するよりもエネルギーの削減に貢献していますよ。同時に、石油や化学原料の消費を減らすことにもつながります。
icebreaker(アイスブレーカー)|ニュージーランド
1994年にニュージーランドで設立されたブランドです。メリノ種という羊の毛を使って商品づくりをしているのが特徴。「メリノウール」と呼ばれ、自然に分解されるだけでなく、温度の調節や消臭効果にもすぐれている素材です。
1997年以降、icebreakerはメリノウールの生産者と公平な取り引きを目指し、長期的な契約を結ぶようになりました。動物福祉に配慮したり、生産の過程がわかる仕組みを取り入れたりして、サステナブルな企業に成長しています。
ウール生産者との公平な取引
メリノウールの生産者とicebreakerの双方に公平な価格を設定。さらに、10年先まで同じ価格での契約を約束しています。
生産者は安定した収入が見込めるので、品質を守るための投資もできるようになりました。一方、icebreaker側には品質のよいウールが手に入るメリットがあります。
動物福祉を重視
多くの製品で羊の毛をつかっているため、動物福祉を大切にしています。
2008年にはアウトドア業界ではじめてミュールジング(幼虫の寄生を防ぐために皮膚を切り取る処置)を禁止しました。代わりに導入された新しい管理方法や治療法は、いまやアウトドア業界全体に広がっていますよ。
メリノウールの生産を管理するために、羊を飼育する環境に以下の5つの条件をもうけています。
- 飢えや乾きがないこと
- 自由に行動できること
- 身を隠すシェルターが確保されていること
- ストレスがないこと
- ケガや病気から保護されていること
icebreakerのウール製品を手に取るとき、ぜひ企業の取り組みに思いを馳せてみてくださいね。
MILLET(ミレー)|フランス
1921年にフランスで設立されたブランドです。当初は食料を運ぶためのトートバッグを製造していました。
1945年から登山用リュックの開発をはじめ、登山家たちと協力しながら商品を改良。1970年代からウェアの領域にも参入をはじめました。現在では、山を中心としたアウトドア用のリュックやウェアが主な商品になっています。
環境に配慮した素材を使用
天然素材やリサイクルされた素材など、環境にやさしい素材を積極的につかっています。また、すべての製品のうち40%の素材はブルーサインを取得。ブルーサインとは、環境・労働・消費者の観点でサステナブルな製品に与えられる認証です。
ほかにも、フッ素化合物を排除するための取り組みも実施。フッ素化合物は水をはじく効果があるので、アウトドア製品によくつかわれています。しかし、自然のなかに残ってしまう物質のため、MILLETでは使用しない製品を増やしていますよ。
倫理的な基準で工場を厳選
生産をおこなう工場は環境面に倫理的な基準をもうけて、厳しく選定。製品をつくるなかで関わる企業も、MILLETが提示している環境配慮の基準を満たしています。
また、ヨーロッパに自社の工場をもつのも環境への配慮からです。店舗までの輸送距離を短くして、環境負荷のあるCO2の排出を減らしています。
HOUDINI(フーディニ)|スウェーデン

「最高の着心地」をコンセプトとして、1993年にスウェーデンで設立されたアウトドアブランドです。耐久テストを重ね、過酷な自然のなかでも耐えられる商品づくりを目指しています。耐久性だけでなく、アウトドアのさまざまなシーンで活躍する機能性にも配慮していますよ。
リサイクル可能な製品づくり
リサイクルできる素材や合成繊維をつかった製品づくりをおこなっています。また、自然に分解される天然素材も積極的に使用。天然繊維と合成繊維は混ぜてつかうことはありません。混ぜてしまうと、リサイクルや生分解ができなくなってしまうからです。
また、つかい終わった製品を堆肥にするプロジェクトもおこなっています。土に埋めると堆肥になるということは、きちんと生分解できる製品だからです。さらに、つくられた堆肥で野菜を育て、レストランに提供する取り組みもおこなっています。
100%循環型のビジネスモデルに挑戦
2030年までに、製造から流通のすべてのプロセスを100%循環型に切り替える予定です。たとえば、海や土のなかにある廃棄物を資源として利用する取り組みをおこなっています。
また、製造から流通に至るプロセスで、トレーサビリティの確立も目指しているのが特徴。トレーサビリティとは、製品をつくる過程が追跡できるように管理されていることです。原料やその生産者、製品のつくられかた、輸送のルートなどをチェックしています。
HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)|ノルウェー
1877年に、ノルウェーの船乗りが工場を設立。船乗りたちの悩みであった、寒さや雨から体を保護するために、防水ウェアの制作をはじめました。翌1878年には、パリ万博でシーマン衣料部門のデザイン賞を獲得。1950年に世界ではじめて完全に防水できるウェアを発売しています。
リサイクルポリエステルを使用
リサイクルされたポリエステルを利用して製品をつくっています。廃棄される予定だったポリエステルを捨てずにすみ、燃やす場合と比べるとCO2の削減が可能になりました。
ポリエステルの原料は石油です。新しくポリエステルをつくる場合と比べ、石油の消費量を少なくできるのも、資源の保全に役立ちますね。
ヨットの帆をアップサイクル
全国のヨットオーナーからつかわれなくなった帆を回収し、バッグやビーチパラソルにアップサイクルしています。アップサイクルとは、捨てられるはずのものにデザインやアイディアで付加価値をもたせ、新しい製品に生まれ変わらせることです。
帆を回収したあとに洗浄し、それぞれの大きさを見ながら新しい製品をつくっていきます。アップサイクルに必要な工程は、すべて自社で実施しているのも特徴です。
AIGLE(エーグル)|フランス
1853年にフランスのロワール地方で創業。地元の職人を集め、天然ゴムのブーツ制作をはじめました。天然ゴムは防水性や耐久性に優れています。やわらかい履き心地も特徴的。長時間履いても疲れにくいブーツとして広まりました。
創業から160年以上経っていますが、レインブーツはブランドを象徴する商品です。現在も伝統的な方法で手づくりされていますよ。また、バッグやウェアなどの多種多様な商品も展開しています。
自社製品を回収してリサイクルに貢献
日本環境設計株式会社がおこなっている「BRING」プロジェクトに参加しています。「BRING」はつかい終わった衣類を回収し、再利用やリサイクルをおこなうプロジェクトです。
AIGLEは店舗で自社製品を回収し、ブーツと服に分類。ブーツはAIGLEが再利用しています。服は日本環境設計株式会社がリサイクル。ポリエステル繊維をポリエステルの樹脂に加工し、新しい服に生まれ変わらせていますよ。
棚田の保全を支援
棚田のお米でつくったヴィーガンアイスクリームを販売する「BEAT ICE」。AIGELはこの取り組みを支援しています。
棚田は山の斜面などに階段状につくられた田んぼのこと。作業がしにくく収穫量も少ないため、放棄される傾向にあります。
「BEAT ICE」は新商品の発売に向けて、クラウドファンディングを実施。クラウドファンディングの寄付へのリターンとして、AIGLEは「BRING」プロジェクトでリサイクルしたTシャツを提供していますよ。
Haglöfs(ホグロフス)|スウェーデン

1914年にスウェーデンで手縫いによるバックパックの制作をはじめました。1916年に正式に会社として設立。耐久性があるシンプルなつくりのバックパックは、農家や漁師など過酷な環境で仕事をする人たちに支持されていきます。
1940年代後半からは、商品のネーミングにもこだわるように。自然やアウトドアに関連する商品名が多く、現在もつづいていますよ。1978年には、寝袋やテントを取り扱う「マンバイス」と合併し、スウェーデンを代表するアウトドアブランドに成長しています。
ブルーサインを取得
2008年にブルーサインの認定を取得しました。ブルーサインとは繊維業界の世界的な認定基準です。ブルーサインの基準をクリアした商品は、環境・健康・安全性への配慮があるとされています。
Haglöfsでブルーサインのラベルがつけられている商品は、認定素材を90%以上、認定アクセサリーを30%以上つかっているという証です。今後もブルーサインの認定素材を増やすことを目指しています。
長持ちする製品づくり
商品を長くつかいつづけられる工夫をしています。たとえば、水をはじく加工や簡単に交換できるジッパーを取り入れるなどです。また、飽きずに長く愛用できるよう、ミニマルなデザインにもこだわりがあります。
長持ちする商品を買うと、シーズンをまたいでも買い替える必要がなくなるのがメリット。商品の生産や廃棄にかかる環境負荷を抑えられますね。
FJALL RAVEN(フェールラーベン)|スウェーデン
1960年にスウェーデンで設立されたブランドです。「重い荷物を入れても快適に背負えるバックパックがほしい」という創業者の思いから、制作が開始されました。1960年代以降は、寝袋やテントなど、バックパック以外の商品も展開しています。
ブランドが目指しているのは、自然の体験をとおして、より多くの人に自然を守りたいという気持ちをもってもらうこと。そのために、商品がサステナブルであることを重要視しているのです。
適切なケアや保管方法を発信
ホームページで正しい洗濯方法や保管方法を紹介しています。ひとつの商品を長くつかうためには、適切なケアが必要です。
とくに、洗濯は商品にダメージを与えたり、水やエネルギーの消費につながったりしますね。必要最低限の回数にする大切さや、適切な方法をつたえているのです。
また、いくつかの商品は強度を増すためにワックスが塗られています。長くつかいつづけられるよう、ワックスの塗り直しの方法もホームページでチェックできますよ。
素材を厳選
機能性と環境へのやさしさが、バランスよく備わる素材を厳選しています。さまざまな素材の環境負荷を確認してリスト化。つねに最新の情報を取り入れて、素材選びに役立てているのです。
基本的に、リサイクル可能な素材やオーガニックな天然素材を優先しています。ただし、いくらサステナブルな素材でも、すぐに買い替えが必要になるようなものはつかいません。さまざまな面から環境への配慮が感じられますね。
Cotopaxi(コトパクシ)|アメリカ
2013年にアメリカでスタートしたアウトドアブランドです。創設者のデイビス・スミスは、もともとアメリカで別のビジネスをおこなっていました。しかし、生まれ育ったラテンアメリカで目の当たりにした貧困を解決するため、Cotopaxiを立ち上げたのです。
商品が購入されると、貧しい人々に恩恵がもたらされるビジネスモデルを考案。さらに、環境に配慮した商品づくりをおこなっています。
積極的な寄付や資金援助を実践
収益の1%を貧困の解決に向けた取り組みにあてています。商品が購入されるほど、社会貢献につながるビジネスモデルですね。
人々の生活を向上させるため、これまでに複数の国への寄付も実施してきました。また、非営利団体への寄付もおこなっています。畑に水を供給するためのポンプを設置するなど、さまざまな活動をサポートしていますよ。
他社の余った素材を活用
他社のアパレルブランドが余らせた素材を活用しています。衣料業界では、衣服を大量に生産する過程で、多くの素材を廃棄しているのが問題視されてきました。
Cotopaxiでは余っている素材をもとに商品のカラーパターンを考えています。そのため、毎年違ったデザインの商品を販売。素材がなくなったら生産も終了します。
捨てられるはずだった素材をつかうと、生産の工程を減らせるだけでなく、廃棄物の削減にもつながりますね。
GREGORY(グレゴリー)|アメリカ
1977年にアメリカのサンディエゴで設立されたアウトドアブランドです。創設者であるウェイン・グレゴリーは、14歳のときにボーイスカウトの活動ではじめてバックパックをつくります。次第にバックパック制作への情熱が高まり、自身のブランドとなるGREGORYを立ち上げました。
GREGORYのバックパックは、人間工学にもどづいたデザインや品質にこだわっているのが特徴。快適な背負い心地や耐久性を追求していますよ。アウトドアシーンだけでなく、日常やビジネスでもつかえるさまざまなバッグを展開しています。
カーボンフットプリントの削減
カーボンフットプリントを減らすことに取り組んでいます。カーボンフットプリントとは、原料の調達から廃棄・リサイクルまでのあいだに排出されるCO2のことです。
カーボンフットプリント削減のため、輸送につかう段ボールのサイズを改良。段ボールのなかで無駄になっていたスペースが減り、より少ない数のコンテナで輸送できるようになりました。
加えて、商品の包装も工夫しています。必要最低限の量になるようなデザインや、環境にやさしい素材を取り入れていますよ。
平等で安全な労働環境を提供
各国にある工場で、労働環境を整備しています。児童労働や人身売買を防ぐだけでなく、抜き打ちで工場の現地調査も実施。工場のスタッフと労働環境や健康、安全面を共有しています。問題がある場合は、解決に向けてしっかりと対処しているのが特徴的です。
Marmot(マーモット)|アメリカ
「生還するためのプロダクト」をコンセプトとする、アメリカ発のアウトドアブランドです。ブランドのはじまりは1971年。カリフォルニアの大学で出会った大学生2人が、寮でパーカーや寝袋をつくりはじめたのがきっかけでした。
1974年、クリント・イーストウッドの映画にダウンジャケットを納品し、ブレイクします。1982年にはウィメンズの商品を発売。アウトドアブランドのなかでも、女性用ウェアのパイオニアとなりました。現在は防水や断熱の技術を生かして、過酷な自然環境でも耐えうる商品を展開しています。
最新技術をつかった長持ちする製品づくり
積極的に最新の技術を取り入れています。防水・速乾・耐熱など、機能性にすぐれた製品を取りそろえているのが特徴。劣化しにくいよう、ひとつの商品を長くつかえる工夫がされています。
ただし、機能性が高くても、環境や人体に悪影響がある物質はつかいません。とくに、水をはじく加工でつかわれるPFCは、環境に残りやすい物質のため、使用を排除しています。
古着の回収とリサイクル
直営店でブランドを問わず古着を回収しています。回収した服はポリエステル素材にリサイクル。新しい服に生まれ変わったり、自動車の内装に利用されたりしています。
ポリエステル以外の素材もリサイクルしますが、まだ着られる服は寄付という形でリユースもしますよ。ゴミの削減や新しい資源をつかわない取り組みに貢献しているのです。
KEEN(キーン)|アメリカ

2003年にアメリカで設立されたフットウェアのブランドです。ブランドのスタートは、設立者のマーティン・キーンがヨットに乗って遊んでいた際に、つま先をケガしたのがきっかけ。つま先を守れるサンダルをつくることを決意し、ブランドを立ち上げました。
最初に発売したモデルは、靴の安心感と、サンダルの手軽さを兼ね備えていることで人気に。ブランドが大きくなっても、いろいろな環境下で快適に遊べる商品づくりを大切にしています。現在はスニーカーのラインナップも豊富です。
自然を守るためのボランティア活動を推進
世界中の海や川でゴミ拾いをするなど、自然環境を守るための活動を実施しています。日本では西表島で旅行者によるゴミ拾いを進めました。ビーチでプラスチックゴミを拾い、石垣港のターミナルに持ち帰ると、アート作品の制作に参加できるというユニークな取り組みです。
ほかにも、野外イベントでゴミの分別とリサイクルの活動を支援。NPO法人とのコラボレーションで、ペットボトルのゴミをつかってアートをつくるイベントをおこなっています。
災害支援を実施
2004年に起きたスマトラ島沖地震をきっかけに、自然災害に対して積極的な支援をしてきました。
2020年に起こった熊本の豪雨では、被災地で活動するボランティア団体に約4,300足のシューズを提供。また、コロナウイルスの流行を受けて、自社工場でつくったマスクを無料配布する取り組みも行なっています。
Deuter(ドイター)|ドイツ
1898年にドイツで創業されたパックパック・ブランドです。1930年に最初のモデルを発売して以来、バックパックはDeuterを代表する製品となっています。
1968年には、世界ではじめてナイロンのバックパックをつくり、軽くて丈夫な素材として主流になりました。現在では、さらに機能性やデザインを高めながら、環境にやさしい製品づくりをしています。
ブルーサイン認証の取得
2008年からブルーサインのパートナーになっています。ブルーサインとは、環境保全はもちろん、働く人や購入者の安全も考慮された製品に与えられる認証です。パートナー工場と共に、ブルーサインの製品づくりに取り組んでいますよ。
はじめてブルーサインの基準をクリアした製品は、キッズシリーズのアイテムでした。また、ペットボトルをリサイクルした素材のデイパックも、2020年にブルーサイン認証を得ています。
工場の労働環境を整備
工場の労働環境を整備する取り組みも行っています。労働者の能力やモチベーションを保つことで、安定した品質につながると考えているためです。
たとえば、ベトナムの工場では、国内の平均賃金より高い給与を支給しています。また、無料のランチや送迎、社宅の提供も実施。労働者が安心して働ける福利厚生がととのえられています。