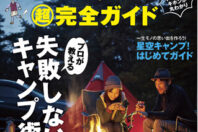低体温症とは

低体温症とメカニズムについて説明します。
低体温症とは命の危険につながる症状
低体温症とは、その文字のごとく身体が冷えて体温が低くなる症状のことです。
登山中の遭難事故の大きな要因のひとつでもあり、これまでに多くの登山者が登山中に低体温症となり、命をなくしています。
また、低体温症は標高の高い山だけで起こるのではありません。登山をする人もしない人も低体温症について理解しておくことが大切です。
低体温症になるメカニズム
登山中に発生する低体温症は、大きく2つのケースに分類できます。1つ目は急性低体温症で、雨に濡れたり沢に落ちたりしてずぶ濡れになり、6時間ほどで急激に体温が低下して低体温症になる症状です。
2つ目は亜急性低体温症で、装備不足などから徐々に身体が冷え、6時間〜24時間ほどで発症します。いずれにしても、身体が冷えて深部体温が35度以下になると低体温症を発症します。
低体温症の症状について

低体温症の症状について、体温別に紹介します。
| 体温 | 低体温症の症状 |
| 35度 | 寒気を感じて身体が震えだします。低体温症であると最初に自覚するのがこの症状です。 |
| 34度 | 震えが激しくなり、顎がガクガクする。足がもつれて歩きにくくなる。ふらついて眠くなる。意識障害が発生する前のこの段階(冷静に考えて判断して動けるうち)で、身体を暖めるなどの対策をとる必要があります。 |
| 33度 | 足がもつれてよく転倒するようになる。意識が遠のいていく(気が遠くなる)。体温が33度以下になると、血液の温度も下がり、酸素を運搬するヘモグロビンが酸素を放出しなくなります。そうなると、脳細胞が酸欠状態に陥り、意識障害が出始めます。 |
| 32度 | 歩けなくなり、立ち上がることも困難になる。意識が混濁してくる。 |
| 31度 | 意識がなくなり、昏睡状態になる。 |
| 28度 | 心肺の停止。 |
どういうときに低体温症になりやすい?
登山での低体温症による遭難事故が多いのは夏場です。冬山の場合は充分な備えをして登るのに対して、夏山の場合は薄着で登ることが多く、寒さに対するじゅうぶんな備えができていないことが原因だと言われています。
つまり油断して山に登り、低体温症になり、遭難するケースがほとんど。
また、真冬に雨が降ることは少ないのですが、それ以外の季節の場合は、雨に濡れることで体温が奪われるため、低体温症が発生しやすくなります。
登山で低体温症にならないための5つの対策

登山で低体温症にならないための対策について、5つの項目別に紹介します。
①雨具を備えて雨に濡れないことが大切
衣類が雨に濡れて体温を奪われることで、低体温症を発症するケースがほとんど。低体温症の対策として、水を通さないアウターを備えて、雨に濡れないようにすることが重要です。
②カロリー摂取と暖かい飲み物
カロリー不足も低体温症の原因になるので、予定よりも数日分多めに食料を用意しておきましょう。あめ玉やキャラメル、チョコレート、カステラなど、カロリーの高いお菓子などは貴重なカロリー源としておすすめです。
また、飲料水とお湯を沸かすためのアルコールストーブなどもあらかじめ用意しておきましょう。ガスボンベは、低温だと燃えないことがありますが、アルコールストーブは、雨の中でもどんなに寒い山でも燃焼してくれます。
③寒さ対策
夏山であっても、冬山と同じくらいの寒さ対策をして臨むことが大切です。アウターを用意して、もしもの天候悪化に備えましょう。
④休息をしっかりとる
疲れが低体温症の症状を悪化させることがあるので、こまめに休息をとり、身体を休めながら登山をすることが大切です。
⑤ツエルトを携帯しておく
避難小屋がないところで、冷たい風雨にさらされて低体温症になるケースが多いようです。あらかじめ小さく折りたたんで携帯することができるツエルトをザックにしのばせておきましょう。
ツエルトは近くに避難小屋がない場合の対応策として使用できます。
チームで登山している場合のツエルトの使いかた
チームで登山している場合には、ザックからツエルトや非常食、飲料、アルコールストーブなどを取り出して、みんなのザックを輪になるように集めて置きます。
ツエルトをひろげてチーム全員が中に入り、ツエルトの端をザックとお尻の間にはさんで、チームで車座になるように座ります。こうすることで、みんなの頭と背中が柱や壁となり車座の中央に空間ができます。
こうしてできた空間で、アルコールストーブを使って湯を沸かしたり、お菓子を食べたり、互いに励ましあったりしながら、天候が回復するのを待ちましょう。
低体温症対策に備えておきたいおすすめグッズ

アライテント(ARAI TENT) ビバークツェルト ソロ
小さく折りたためて、蒸れにくく、動きやすいポンチョがおすすめです。ツエルトのようにして使うことも可能。
Juza Field Gear Em-Shelter I UL/エム・シェルター
中に入った人やザックなどを壁にして自立するツエルトです。170gと非常に軽くコンパクトに折りたためます。
trangia(トランギア) アルコールバーナー
アルコールストーブの代名詞的な存在、トランギアのアルコールバーナーです。25分間燃焼するのでお湯を沸かすのに便利。
燃料用 アルコール 500ml x 3個セット
燃料用アルコールです。メタノール、エタノール、イソプロパノールを配合しているので、手の消毒などには使用できません。

ライター
Greenfield編集部
【自然と学び 遊ぶをつなぐ】
日本のアウトドア・レジャースポーツ産業の発展を促進する事を目的に掲げ記事を配信をするGreenfield編集部。これからアウトドア・レジャースポーツにチャレンジする方、初級者から中級者の方々をサポートいたします。