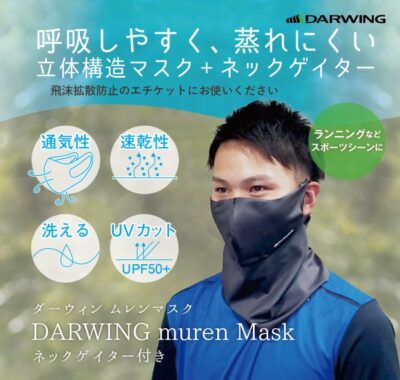冬山でゲイターが欠かせない理由は?

ゲイターは靴とスボンの間のすき間を覆うようにつけるもので、素材は違いますがダンスでつかうレッグウォーマーに似ています。
ゲイターの役割は石、枝などや、雨や雪などが入るのを防ぐこと。
もう1つの重要な役割は、靴や足が濡れたりするのを防ぐことです。
登山では標高が高いと気温も低くなりますし、靴や足が濡れてしまうと、そこからどんどん体温が奪われて、低体温症になってしまうリスクがあります。
低体温症のリスクを軽減したり、冬山での体温調節のために、ゲイターは必須アイテムなのです。
ゲイターの選びかた

ゲイターを選ぶときにチェックしたいポイントが、長さ、素材、止めかたの3つです。
ひとつひとつを見ていきましょう。
長さで選ぶ
ゲイターの長さは、ショート、ミドル、ロングの3種類があります。
ショートは、20〜30cmぐらい、足首とその上ぐらいまでの長さ。
夏のトレッキングや秋口などちょっと涼しくなったぐらいならこれでOKです。
セミロングは、25〜35cmぐらい、足首とヒザの中間ぐらいの長さ。
ロングに比べると軽量ですが、ずりおちてくることがあるところがデメリットです。
ロングは、35〜45cmぐらい、ヒザ下ぐらいの長さ。
雪山にはこれがおすすめ、雪がたくさん積もっているような場所でも足が濡れるのを防いでくれます。
ゲイターで多いのは、ショートとロングです。
セミロングを出しているメーカーもありますが、種類は少ないのが特徴。
ショートは、主に小石や泥などが靴に入らないために使われることが多く、ロングは、深い雪や泥、豪雨、そして草木におおわれた地域を歩くときなどにつかいます。
真冬につかう場合は、厚着することを考えて、あまりぴったりのサイズではなく、少しゆとりがあるサイズを選ぶようにするといいでしょう。
素材で選ぶ
素材も、その用途によって種類はさまざまです。
夏や秋口用ならば、体温管理につかうというよりも、小石などが入らないようにするのが目的だと思います。
その場合、ショートゲイターで十分で、つけていても蒸れない通気性と、動きをさまたげない伸縮性のある素材がおすすめです。
冬の時期ならば、ロングのゲイターで雪や雨を考えた防水性の素材がよく、防水性で選ぶならゴアテックスがおすすめ。
ゴアテックスは値段は高いですが、防水性はピカイチ。
また冬の登山だと、アイゼンをつかうことも考えられますが、アイゼンを装着していると、はずみでアイゼンの爪の部分が、ゲイターにひっかかったりして、裂けてしまうこともあります。
そういうことを考えると、なるべく耐久性の高い素材を選ぶことが大切です。
ジッパーやベルクロなど止めかたで選ぶ
ゲイターの留具は、ジッパーのほかにマジックテープによるベルクロの2つのタイプが多いです。
これはつける人の好みともいえますが、ジッパーをいちいちはめるのが苦手という人や、雪山では手袋をはめたままではやりにくいという理由から、ベルクロ派が多いかもしれません。
ジッパーとベルクロの併用タイプもありますが、しっかりと止められるメリットもありつつ、着脱は少し面倒かもしれません。
おすすめのゲイター

サロモン ゲイター Trail Gaiters Low
サロモンは、フランス発のマウンテンスポーツブランドです。
スキーやスノーボード用品はもちろん、ハイキングやトレイルランニング用の靴やアイテムを多く発売しています。
トレイル ゲイターローは、一番短いタイプのゲイターで、トレイルランニングやトレッキングのときの砂や小石が靴に入るのを防いでくれます。
ベルクロでとめるタイプなので、着脱が簡単で、あまり締めつけないので、ランニングや歩くときの動きをさまたげません。
また小さいので、持ち運びにも便利ですし、必要がなくなったら、ポケットなどにも入る大きさというところも魅力です。
ISUKA(イスカ)ゴアテックス ライトスパッツ フロントジッパー
ISUKAは、寝袋とシュラフの専門メーカーです。
ライトスパッツは、ストレートデザインで、素材は強い防水効果のあるゴアテックスです。
着脱しやすい全面ジッパーで、下側からも開けたり閉めたりできるので、靴紐を直したりしたいときにも便利な作りになっています。
上部にはひものアジャスターがついていますので、季節や服装によってしめたり、延ばしたりすることもできます。
また持ち運びに便利な専用の収納ケースつき。