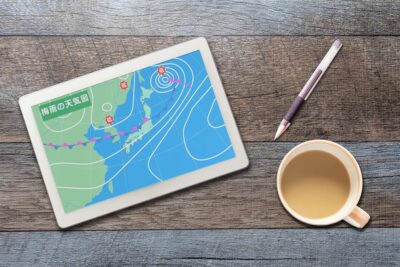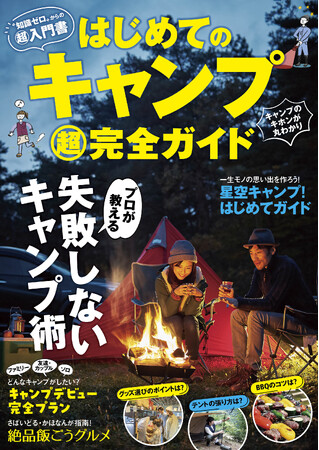身近であるのに、深掘りすればするほど興味深い昆虫である「チョウ」。チョウが好きになると、同じ時期に決まった場所で発生する姿を毎年見たくなり、年ごとの増減も気になってきます。チョウを入口に身近な自然環境や昆虫の世界への興味が広がれば、アウトドアがますます充実するはず。今回は、そんなチョウの生態や生息地との関係、興味深い種類について紹介していきます。
チョウの生態を紹介

イチモンジセセリ
チョウは小さな卵から生まれ、幼虫、蛹という段階を経て成虫になることはよく知られています。これらの段階で、まったく異なる姿と役割を持っているのがおもしろいポイントです。
孵化したばかりの幼虫、いわゆる芋虫はとにかく食べることに専念し、脱皮を繰り返しながらどんどん成長しています。彼らのミッションはただ一つ、ひたすら食べて大きくなること。
幼虫は充分に成長すると、やがて動かなくなり最後の脱皮をして蛹へと変化します。一見すると、休んでいるかのように見えますが、蛹の中で進行しているのは奇跡の大変身です。
幼虫の体はいったん分解されてドロドロになり、細胞が再構築されることにより、成虫の羽や触角、複眼などが形成され、まったく違う姿へと変貌を遂げます。
成虫の特徴は、繁殖のための器官を備えていることです。蛹から出てきたチョウは、羽を広げて乾かし、やがて飛び立ちます。飛ぶことで行動範囲を広げ、新たな子孫を残し命をつないでいくのです。
このように、チョウは一生を通して驚異の変化を遂げています。さらに、花の蜜を吸うときに花粉を運ぶなど、植物の受粉にも貢献し生態系の中でも大切な役割を果たしています。
チョウの種類は環境を反映

アオスジアゲハ
チョウが生息できる環境は、分布している植物に大きく依存しています。その理由は、幼虫が食べる食草は、チョウの種類によって決まっているためです。
例えばモンシロチョウはキャベツなどのアブラナ科、アゲハはサンショウやミカン類などと決まっていて、葉っぱなら何でも食べるわけではありません。
反対に、生息するチョウの種類によって、そこがどんな環境なのかを知ることもできます。環境ごとに分かりやすいチョウの例を紹介します。
街のチョウ

ツマグロヒョウモンのメス
街の中には、街路樹や公園、花壇に植えられた植物を好むチョウが飛んでいます。街路樹に多いクスノキはアオスジアゲハの食草です。光沢のある水色のラインが美しい羽をもつアオスジアゲハは、大きめなのでよく目立ちます。夏になると、都会でも普通に見られます。
花壇のパンジーは、ツマグロヒョウモンの食草です。幼虫はトゲトゲした姿ですが毒はなく、触っても大丈夫。飼育すると、キラキラ輝く10粒の斑点模様がある蛹も、近くでじっくり観察できます。
成虫はオレンジ色の羽に黒い斑点があり、メスは羽の先が黒っぽい大きめのチョウで、見られる時期も長いため見つけやすい種の一つです。北にむけて分布を拡大中で、関東では2000年ごろから普通にみられるようになっています。
畑のチョウ
畑のチョウといえば、アブラナ科の植物を食草とするモンシロチョウです。キャベツ、白菜、ブロッコリー、小松菜、大根、カブなど、これらはすべてアブラナ科。つまり野菜の害虫でもあるわけですが、畑の上でモンシロチョウが何匹も飛んでいるのはのどかな光景です。
チョウを愛する身としては、殺虫剤が使われるのは心が痛みます。薬剤を使わなくても、ネットをかけることで成虫が葉っぱに産卵するのを防ぐことが可能です。
空き地や草原のチョウ

モンキチョウ
市街地の草地では、タデ科を食草とするベニシジミ、マメ科の植物を好むキタキチョウ、シロツメクサなどを食べるモンキチョウなどがメジャーな種です。
一方、ススキ野原などは減っているため、イチモンジセセリやギンイチモンジセセリ、オオチャバネセセリは減少傾向です。
また、オオルリシジミ、ウスイロヒョウモンモドキなど、草原環境の特定の植物を食草としている種は、絶滅危惧種となっている場合もあります。
雑木林のチョウ

オオムラサキ
雑木林や里山環境のシンボルとして、各地で保全されているのが国蝶であるオオムラサキです。幼虫はエノキを食草とし、成虫はカブトムシなどと同じようにクヌギ・コナラの樹液に集まります。
また、コナラ・カシワ・クヌギを食草とするアカシジミも、雑木林で見られる種です。アカシジミは初夏のころ、オオムラサキは夏が本番となるころに成虫が見られます。
近年では開発や管理不足により良好な環境の雑木林が減っているため、これらの種は簡単には見られなくなっています。見つけられたら、かなり幸運といえるでしょう。
見つけてうれしいチョウ

ウスバシロチョウ
チョウに興味をもつと、種類が気になってくるかもしれません。きちんと種を同定するには、捕虫網で捕まえたり写真を撮ったりして、図鑑と見比べる必要があります。
春から秋まで長期間見られる種もありますが、季節限定のチョウや珍しいチョウは観察場所の情報を集めて探しに行ってみるのもお勧めです。季節と場所によってはいつか出合えるかもしれない、実物を見られたらうれしい種を紹介します。
春限定のウスバシロチョウ・ツマキチョウ
新緑を過ぎたころに現れるウスバシロチョウは、鱗粉(りんぷん)が少ないため透明感のある翅(はね)が特徴です。翅の付け根の黄色い体毛も目立ちます。食草はムラサキケマンで、成虫は開けた草地の上を滑空し飛び方も独特です。
ツマキチョウはモンシロチョウに似ていますが、やや小さめで、オスの翅の先が黄色いのが種名の由来です。止まった時に見える翅の表側は、緑色の雲上の模様があり、何ともいえない美しさがあります。
幼虫はタネツケバナなどアブラナ科を食草とし、新緑のころに成虫となりますが、気をつけていないとモンシロチョウと見間違えて素通りしてしまうでしょう。
ゼフィルスと呼ばれる美しいシジミチョウ

エゾミドリシジミ
シジミチョウといえばカタバミを食草とするヤマトシジミが一番身近な種ですが、緑色や青色の金属光沢の翅をもつミドリシジミの仲間はゼフィルスと呼ばれ特別な存在です。
ゼフィルスの呼び名は、初夏のころに美しい輝きを放ちながら飛ぶ姿から、ギリシャ神話の西風の神ゼピュロスに由来しています。コナラ、ミズナラ、カシ類などブナ科の樹木を食草とする種が多く、雑木林などが生息地です。
昼間は葉の上で静止していることが多いですが、夕方になると活発に飛び回るため、生息地が分かっていれば辛抱強く待っていると見られる可能性があります。
長距離移動するアサギマダラ

アサギマダラ
長距離を移動するチョウとして知られるアサギマダラは、大型であさぎ色(水色)が美しく、ゆったりと飛ぶ姿も優美です。千葉県・茨城県以南の照葉樹林で越冬して、春になると北へと向かい、夏は山地の樹林に滞在。秋には南下するといわれています。
2千キロ以上を飛んだ記録もあり、移動に関するマーキング調査も各地で行われています。ヒヨドリバナやフジバカマを植えておくと、夏の盛りを過ぎたころに成虫が立ち寄ってくれるかもしれません。
参考
完全変態する昆虫は、なんであんなにまったく別の虫のように体を変えることができるのですか?│コカネット(誠文堂新光社)
フィールドガイド日本のチョウ|誠文堂新光社

ライター
曽我部倫子
東京都在住。1級子ども環境管理士と保育士の資格をもち、小さなお子さんや保護者を対象に、自然に直接触れる体験を提供している。
子ども × 環境教育の活動経歴は20年ほど。谷津田の保全に関わり、生きもの探しが大好き。また、Webライターとして環境問題やSDGs、GXなどをテーマに執筆している。三姉妹の母。