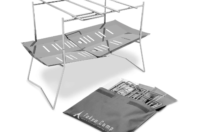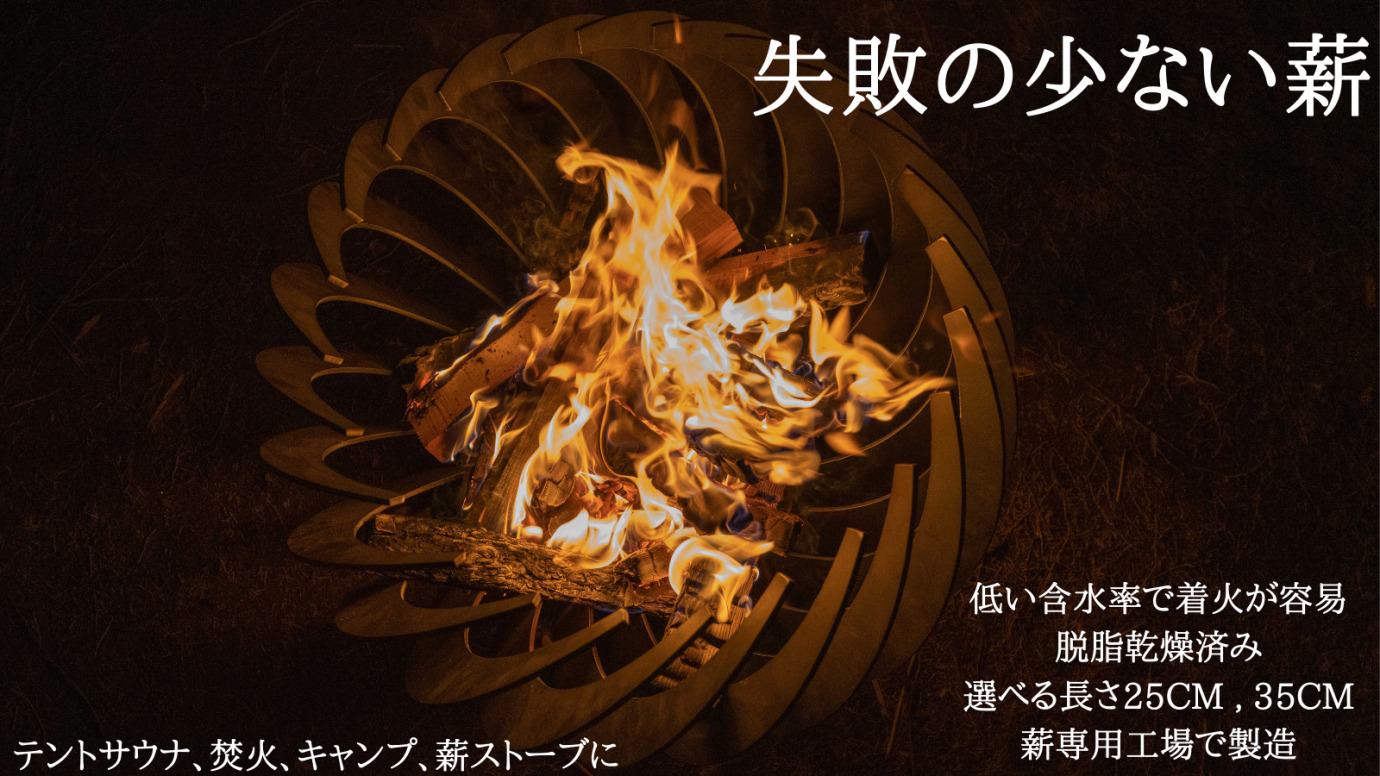薪の種類は針葉樹と広葉樹に分けられる
一見どれも同じに見えますが、焚き火で使われる薪は「針葉樹」と「広葉樹」に分けられます。
それぞれにメリットやデメリットがあるため、用途や目的に応じた使い分けが重要です。また、薪の割り方によっても、火のつき方や燃焼時間が異なります。針葉樹と広葉樹のメリット・デメリットを理解した上で使い分けると、焚き火がもっと楽しくなるでしょう。
針葉樹の特徴

針葉樹とは、スギ・マツ・ヒノキなど、葉が針のように細く尖っている木です。広葉樹よりも安価で手に入れやすいのが特徴です。キャンプ場では、一束500円前後で売られています。
針葉樹の薪は、油分や空気を多く含んでいるため燃えやすく、焚き付けに適しています。なお、松ぼっくりも針葉樹と同様に油分や空気を多く含んでいることから、焚き付けにぴったりです。
その反面、火持ちが悪く、煙や匂いが多い点がデメリットと言えるでしょう。また、ススにも注意する必要があります。針葉樹の薪での焚き火で、コッヘルなどの調理器具を直火にかけると、ススで真っ黒になる場合があるので気をつけてください。
針葉樹の薪を使用する際は、特徴を理解し、使いどころを心掛けることが大切です。たとえば、着火時は針葉樹の薪を用い、その後は火を維持するために広葉樹の薪を使うなどするとよいでしょう。また、針葉樹の薪は煙や匂いがでやすいため、衣服に匂いがうつらないよう風向きを意識してください。
広葉樹の特徴

広葉樹とは、サクラ・ケヤキ・ブナのように葉が平らなタイプの木です。針葉樹に比べて幹の密度が高くて着火しにくい傾向がありますが、長時間燃えやすい点が大きなメリットです。
針葉樹に比べて油分やヤニが少ないため、煙をおさえられます。価格は、一束700円程度と針葉樹よりも少し高めです。ゆっくりと焚き火を楽しみたいなら広葉樹がおすすめです。長時間燃え続けるだけでなく火力も安定するので、焚き火料理に適しているでしょう。
広葉樹の薪を選ぶ際は、しっかりと乾燥しているかを確認してください。十分に乾燥した広葉樹の薪は火持ちが良く、煙が少ないのが特徴です。また、薪の割り方にも注意が必要です。針葉樹に比べて着火しにくいため、少し小さめに割って使用しましょう。
代表的な針葉樹と広葉樹
薪は、針葉樹と広葉樹に分けられますが、木の種類によっても特徴が違ってきます。ここからは、焚き火でよく使われる木の種類と特徴を詳しく紹介します。
針葉樹

針葉樹のなかでも代表的な、スギ・ヒノキ・マツを紹介します。
スギ
全国各地で大量に植林されているスギの木を用いた薪は、安価で入手しやすいといえます。スギの薪は軽くて柔らかいため、薪割りが容易な点が魅力。取り扱いやすいので、焚き火の初心者におすすめです。
また、着火しやすいため、焚き付けに適しているのが特徴です。ただし、燃えやすいため長時間の燃焼には向いていません。持続的な火力が必要な場合は、広葉樹の薪との併用を検討してください。
ヒノキ
高級な木材として広く知られているヒノキは、薪としても使用されます。乾燥が比較的早く進み、よく燃えるのが大きな特徴です。しかし、スギと同様に燃焼時間が短い傾向があります。
ヒノキの薪は、焚き火や薪ストーブ用の木材として人気が高いといえます。キャンプの際は、その香りを存分に楽しめるでしょう。ヒノキ独特の香りは、キャンプでリラックスしたいときに一役買います。
なお、継続的な火力が必要な場合は、広葉樹の薪と組み合わせるのが良いでしょう。広葉樹の薪と併用することで、焚き火や料理を長時間楽しめます。
マツ
マツは油分が多くて着火しやすいうえ、スギやヒノキに比べて燃焼時間がやや長いのが特徴です。さらに、火力が強いのも魅力です。
一方で、ススや煙が出やすい傾向があります。ススや煙による衣服やテントなどへの匂いうつりが気になる人は、スギやヒノキの薪を使用するのがよいでしょう。
広葉樹

ここでは、代表的な広葉樹であるナラ・カシ・クヌギ・ケヤキの4種類を詳しく紹介します。購入時の参考にしてください。
ナラ
ナラの木は、ドングリを実らせる木として広く知られています。ホームセンターやアウトドアショップで売られていることが多いため、比較的簡単に入手しやすいでしょう。また、燃焼時間が長いので、頻繁に焚き火を楽しむキャンパーからよく使用されています。
ナラの薪は火力が安定しているという特徴があるため、焚き火や薪ストーブにぴったりです。また、密度が高いので、長時間燃焼し続けます。そのため、長時間のキャンプファイヤーや薪ストーブでの暖房に非常に適しているでしょう。
薪割りは比較的容易で、様々なサイズに加工できます。小さなサイズにすれば焚き付けに使えるでしょう。
カシ
カシの木は、抜群の火持ちの良さと煙の少なさから、薪の王様として高く評価されています。密度が高くて硬いため、薪割りには多少の労力が必要です。しかし、一度着火すると長時間にわたって安定して燃焼するという特徴があります。そのため、薪ストーブでの使用に特に適しており、効率的に燃焼する熱源として重宝されています。
カシの木は成長と乾燥に時間がかかるため、市場での流通量は限られがちです。そのため、他の木材に比べてやや高価です。しかし、火持ちの良さと煙の少なさを考えた場合、コストパフォーマンスに優れていると言えるでしょう。
クヌギ
カシと同様に密度が高くて硬く、火持ちが良い高級な薪として知られています。クヌギの木は、カシと比較して成長が早いため、薪用としての植林が昔から行われてきました。ススや煙が少ないのが特徴です。また、ゆっくりと燃えることでほのかな香りを放つため、リラックスできるでしょう。また、香りでキャンプの雰囲気を演出できます。
クヌギは、薪としての使用に特に適しており、薪ストーブやキャンプファイヤーなど様々なシーンで重宝されます。燃焼時間が長く、ススや煙が少ないため、屋内での薪ストーブに向いているでしょう。
ケヤキ
ケヤキの木は火持ちの良さと火力の強さが優れており、広葉樹の中では比較的着火しやすいのが特徴です。青みがかった美しい色の炎で燃えるため、焚き火をたしなむ多くのキャンパーから愛用されています。一方で、乾燥すると非常に硬くなって斧がなかなか入らないため、薪割りに苦労するでしょう。
上述したような燃焼特性のため、焚き火や薪ストーブに特に適しています。燃焼時間の長さと火力の強さは、屋外でのキャンプファイヤーや寒い夜のキャンプにぴったりでしょう。また、簡単に着火できるため、焚き火の準備をスムーズに進められます。
薪の割り方や組み方による燃焼の違い

薪の割り方や組み方は、燃焼の仕方に大きな影響を与えます。ここまでの説明から、薪の種類によって火力の強さ・火付きの良さ・燃焼時間などに違いがあることが分かったかと思います。
一番の理想は、針葉樹と広葉樹の2種類を併用する方法です。最初に着火しやすい針葉樹で焚き付けて、その後は長時間燃焼しやすい広葉樹を使いましょう。2種類の薪を併用することで、長時間快適に焚き火ができます。
しかし、時には針葉樹か広葉樹のどちらか一方しか手に入らない場合があるでしょう。そのような場合は、薪の割り方を工夫してください。
着火はしやすいものの、長い時間燃えにくい針葉樹しか手に入らない場合は、できるだけ大きく割って火持ちを良くしましょう。また、着火はしにくいが、長時間にわたって燃えやすい広葉樹の場合は、細かく割るのを推奨します。
また、薪の組み方によっても燃焼の仕方に差がでます。井げた状に組む「井げた型」や、三角に組む「合掌型」は勢い良く燃えるので、早く暖を取りたい時やキャンプファイヤーに向いています。しかし、火力が強いので長時間の焚き火や調理には適していません。
焚き火をゆっくりと楽しみたいのであれば、枕木を置いてその上に横に薪を並べる「並列型」がおすすめです。安定した火力で長時間燃え続けるので、焚き火料理に向いていますよ。

異なる種類の薪を組み合わせた温度調節のやり方
先ほど、火のつけ方としては着火しやすい針葉樹で火を起こし、その後長時間燃えやすい広葉樹を加えて火を安定させる方法が理想だと説明しました。ここではより詳細に火を安定させるやり方や、火を弱くするやり方について説明します。
火を強くしたいとき
基本的にはその後火が弱くなってから再び火を強くしたい場合にも、針葉樹で火を強くし、広葉樹でそれを持続させる、というやり方で火を維持させます。最初に針葉樹を追加することで、火を再び強くし、燃焼を活発化させます。針葉樹は燃焼が速く、素早く炎を生み出すため、火を再活性化させるのに適しています。
その後、火を持続させるためには、広葉樹を燃やすことで、長時間の熱を供給し続けることができます。広葉樹は燃焼が遅く、持続性が高いため、火を維持させるのに効果的です。
また、薪の太さにも着目しましょう。着火時や火が小さくなったときは大きめに割った太い薪を使い、火が着いたらそれを安定させるために細かく割った薪を使用するのがおすすめです。
火を弱くしたいとき
反対に、火を弱くしたい場合には、以下を試してみるとよいでしょう。
まず、火を小さくするためには、燃焼中の薪の量を調整します。火が大きすぎる場合は、薪を減らして火力を調整しましょう。小さな薪や割った小片の薪を追加することで、火力を抑えられます。
また、燃焼中の空気の流れを制限することも効果的です。風防や風よけを使ったり、通気口を一部閉じることで、火の勢いを調整できます。
さらに、薪の配置や火周りの構造を調整する方法もあります。薪を燃焼中心から外側に寄せたり、薪を積み上げる高さを低くしたりすることで、燃焼面積を減らし、火を小さくすることができます。
最後に、火を小さくする方法として、火の上に薄い金属板や石などを置いて火を覆う方法もあります。これにより、酸素の供給が減少し、火力が抑えられます。
このように、異なる種類の薪を組み合わせることで、火の維持や温度・火力の調節を効果的に行うことができます。特に、針葉樹と広葉樹の組み合わせは、火の起こし方から火の維持まで、キャンプやアウトドア活動での薪の使い方を理解する上で重要なポイントです。
【薪の種類を選ぶ前に】薪はどこで買う?
焚き火で使う薪を手に入れる方法はさまざまです。キャンプ場では、施設内で薪を提供していることがあり、手軽に入手できます。
また、ホームセンターやガーデンショップでも焚き火用の薪が販売されています。通販サイトでは、様々な種類やサイズの薪を選ぶことができ、便利な配送サービスも魅力です。
森林組合や薪専門店では、地元の木材を使用した高品質な薪を見つけられます。
キャンプ場
キャンプ場での購入は便利で手軽な方法です。多くのキャンプ場では、現地で焚き火用の薪が販売されています。一般的に、キャンプ場内の売店や管理事務所で薪を取り扱っています。
キャンプ場での調達のメリットは、車が汚れないことです。現地での調達になるので車で運ぶ必要がなく、その場で必要な分だけを買い、すぐに使えます。
一方で、価格はキャンプ場によって異なります。ホームセンターや通販より安く買える場所もあれば、割高の場所もあり、当たり外れが激しい点はデメリットです。
決済方法も一部のキャンプ場ではクレジットカードやQRコード決済に対応していますが、現金の場合が多いです。
他にも、薪が外に置かれていて水分を含んでいたり、薪の形がバラバラであったりするため、薪を選ぶ際には注意が必要です。
サービス面では、キャンプ場スタッフが焚き火の始め方や注意事項を教えてくれることもあり、初心者でも安心して楽しめます。
また、キャンプ場が提供する薪は、地元の木材や環境に優しい材料を使用していることも多く、購入することで地元産業や持続可能な資源利用に貢献することが期待できます。
手軽に買えることはメリットですが、キャンプ場によって価格や品質にばらつきがあるため、キャンプ場で薪を調達するのは持ってきたものが足りなくなった場合がよいでしょう。
ホームセンター
ホームセンターはアウトドア用品を購入する際の定番の選択肢です。ホームセンターには多様な薪の品ぞろえがあり、自分の目的に合った薪の種類やサイズを選択できます。価格も比較的手頃で、通常はキャンプ場や薪専門店よりもリーズナブルです。
また、セット商品やバラ売りなど、柔軟な購入オプションがあります。
一方で、ホームセンターでの購入にはデメリットもあります。品質面では、キャンプ場と同様に、各ホームセンターによって乾燥度合いや木材の種類が異なることがあります。焚き火の楽しみに影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
また、購入した薪の運搬が自己責任となり、車での移動が必要な場合はその手間も考慮する必要があります。
ホームセンターで薪を購入するメリットは、幅広い品揃えと手頃な価格で手に入ることです。デメリットは、品質の一定性や輸送にかかる手間があることです。比較的手軽に入手できるため、アウトドア初心者や短期のアウトドア活動には適していますが、本格的なキャンプや長期間の利用を考える場合は、品質を優先した購入先を検討することが重要です。
通販サイト
通販サイトでは、様々な種類やサイズの薪が豊富に揃っており、地域に限らず広範囲で商品が手に入ります。そのため、特定の木材を求めたり、地域限定のものを手に入れることが可能です。価格も競争が激しいため、一般的にはリーズナブルで、時折セールや特典が用意されていることもあります。
通販のメリットとして、豊富な品ぞろえや手軽な購入手続きが挙げられます。また、自宅まで商品が配送されるため、購入してから家に運ぶまでの車での移動や運搬の手間がかかりません。他にも、薪の長さや乾燥度についても細かく指定して買えます。
一方で、商品を実際に確認し、品質を確かめることが難しい点がデメリットとされます。木材の状態を細かく指定できるとはいえ、本当に自分の望み通りのものが配送されるかはわかりません。選択肢が多い反面、品質の一貫性には注意が必要で、商品の見極めはじっくり行うべきでしょう。
森林組合・薪専門店
森林組合や薪専門店で焚き火用の薪を購入することで、高品質で環境に優しい木材を手に入れられます。森林組合や薪専門店では、通常、地元の木材を使用した薪が販売されているため、燃焼効率の高さが期待できます。
品質にこだわる人や、森林の保全に配慮したい人におすすめの購入先です。
他のメリットとして、品質の一貫性が高いことも挙げられます。また、通販やホームセンターよりも専門的な知識を持つスタッフがいる場合が多く、選ぶ際にアドバイスが受けられることも魅力です。
さらに、地域の特産物や伝統的な薪も購入できるため、地元の資源を支えることもできます。
一方で、価格が他の販売先よりもやや高いことがあり、品ぞろえが他の販売先に比べて多様ではないことがデメリットとされます。また、一部の場所では取り扱い店舗が限られていることも考慮が必要です。しかし、これは地元の資源を利用することで生じる地域性の特徴でもあります。
森林組合や薪専門店で薪を購入することは、品質と環境への配慮を大切にする人にとって、焚き火体験を一層豊かなものにする良い方法と言えます。
無料で調達できる?
様々な場所で購入できる薪ですが、無料で手に入ることもあります。
- 伐採ボランティア組合に加入する
- 地元で林業を営んでいる人や製材屋と交流する
以上の2つの場合には無料で薪を調達できるかもしれません。
まず、地域によっては伐採ボランティアの組合がある地域もあります。会費を払う必要がありますが、伐採に参加して原木を分けてもらえれば、通販や実店舗で購入するよりコストパフォーマンスには優れていると言えるでしょう。
組合によっては、伐採された倒木を好きなタイミングで取りに行けるところもあるため、近隣に伐採のボランティア組合がないか調べてみてください。
2つ目は、地元の製材屋や林業を営む人に話を聞いて、分けてもらうという方法です。事業所によってはある程度の木材が溜まると無償提供しているところや、伐採した原木をいつでも分けてもらえるところがあるようです。
地元の人との交流をきっかけに以上のような機会が生まれることもありますが、あくまで伐採した人の厚意によって木材を分けてもらえることに留意しましょう。
薪の種類の選び方と注意点
ここまでで針葉樹・広葉樹の特徴を見てきました。それぞれの燃え方を理解できたかと思いますが、その燃え方を踏まえて、自身のキャンプシーンに合った薪を選ぶにはどこに注意すべきかを説明します。
薪を選ぶ際には、自身の用途によって、サイズ・太さ・乾燥度を選びましょう。
用途に合わせて選ぶ
キャンプで薪を使用する際は、用途やシーンによって適した薪の選び方があります。針葉樹の薪は着火が早く、火力が上がりやすいという特徴があります。しかし、日持ちが悪く、煙やにおいが強いので、長時間の使用には向きません。そのため、短時間の焚き火や、火力が必要なバーベキューに適しています。
広葉樹の薪は着火が難しく、価格が高めですが、長時間の火持ちと煙の量が多くないことが特徴です。焚き火でゆっくりと暖をとりたい場合や、鍋料理、ピザなどの料理を焚き火でじっくりと調理したい場合、薪ストーブを使用する際に向いています。
また、両者を組み合わせることも一つの方法です。先ほども説明したように、針葉樹の薪で着火し、その後広葉樹の薪に火をうつして使用すると、安定して火を維持できます。
シーンや使用目的に応じ、針葉樹と広葉樹の薪を組み合わせ、焚き火以外の用途も考慮して持参することで、キャンプのさまざまな場面で効果的に利用できます。バーベキューや焚き火、調理シーンなどを考慮し、適切な量・配分の薪を用意することが重要です。
長さ・太さ
焚き火に使用する薪の長さと太さには注意して選ぶことが重要です。まず、長さはキャンプ場や設営場所の焚き火台、もしくは自身が持ってきた焚き火台のサイズに合わせて選びましょう。
焚き火台の直径より長すぎるものは、焚き火の途中で燃えたまま落ちてしまう可能性があるため、直径より5から10センチほど短いものにするのがおすすめです。
また、薪の長さは均一にしましょう。長さが異なると火の広がりがまばらで、遅くなることがあります。
薪は細いものから燃やし、徐々に太いものを燃やしていきます。そのため、異なる太さの薪がバラバラに入り乱れている状態だと、効率的に火をつけられません。細い薪、中程度の薪、太い薪を分けておくことをおすすめします。
太さを分けて用意することで、火力の調整がしやすくなります。太さの目安としては、細い薪は直径2センチ、中くらいの薪は5センチ、太い薪は10センチほどで考えるとよいでしょう。
着火剤の上に細めの薪を置き、火をつけてから徐々に標準の太さの薪や太めの薪を投入することで、火を長時間維持させられます。
含水率は20パーセント以下
薪を使う際は、薪がどれだけ乾燥しているかが重要です。薪の含水率が高い、つまり、薪が湿っている状態だと、薪の水分を蒸発させた後に薪自体が燃やされます。
水分を蒸発させるエネルギーを使う分、火力を上げるために使うエネルギーが少なくなってしまうのです。また、薪に含まれる水分が蒸発する際には大量の煙が出るため、火に近寄れなくなってしまいます。
火力が上がらず煙が多く出る不完全燃焼の状態にならないように、十分に乾燥している薪を使いましょう。含水率の目安としては20パーセント以下が適切です。
通販やホームセンターで購入できる焚き火用の薪は、含水率が20パーセント以下に抑えられたものが多いですが、念のため確認して購入しましょう。
伐採されたばかりの木は含水率が50パーセントほどなので、1年から2年ほど乾燥させる必要があります。乾燥している薪は、持った時に軽い・表面にひびが入っている・薪同士で叩くと乾いた音がするなどの特徴があるので、確かめてみましょう。
薪選びの注意点
薪として燃やしてはいけない木材がいくつかあるため注意しましょう。燃やしてしまうと有害な成分を発生させてしまい、健康被害が出てしまうかもしれません。
燃やしてはいけない木材を2つ紹介します。
- キョウチクトウ
- ユズリハ
キョウチクトウ(夾竹桃)は、6から9月に桃の花に似たピンクや白色の綺麗な花を咲かせる植物です。園芸用として広く親しまれており、公園の花壇や街路樹などに植えられていることが多いです。
しかし、茎、葉、花、根の全てが有毒であり、燃やしてしまうと強い毒性を持つ有毒ガスを放出してしまいます。毒には即効性があるため、ガスを吸い込むとすぐにめまいや吐き気などの症状が表れます。絶対に使わないようにしましょう。
2つ目はユズリハです。縁起の良い木として有名なユズリハですが、毒性のある木であり注意が必要です。日本各地に植生しており、剪定などで葉を落とした枝はサイズ感が焚き火に適していると感じるかもしれません。
しかし、家畜が死亡した事例があるため、人間に影響がある可能性もあります。ユズリハに触った手で食品を触ることのないように、十分に注意しましょう。
特徴はブルーベリーのような実をつけていることと、大きな楕円形の葉です。似たような特徴の木には触れないように注意が必要です。
以上2つの植物を中心に、アウトドアで焚き火を行い中毒症状に陥ってしまった事例がいくつかあります。薪が足りなくなった際に、キャンプ場に落ちている木枝を使うことは避けましょう。
薪の種類の見分け方
お店に行けば薪が針葉樹か広葉樹か書いてある場合が多いですが、明記されていない場合もあります。そこで、針葉樹か広葉樹のどちらであるかを見分ける方法を説明します。
見分ける際に見るべきポイントは、年輪・重さ・樹皮の3つです。針葉樹は年輪が薄いのに対して、広葉樹は年輪が厚いという違いがあります。
また、針葉樹は密度が低いことから広葉樹より軽いです。反対に、広葉樹は密度が高く、針葉樹に比べて重いです。
樹皮は、針葉樹であれば手で引っ張って簡単に剥がれるほど薄いのに対して、広葉樹は分厚くしっかりとついているため、手で剥がすのは難しいです。
明記されていることが好ましいですが、もし針葉樹と広葉樹のどちらか分からなくなった場合には、以上を参考に見分けてみてください。
薪の火付にオススメのアイテム
着火剤
薪で火を起こす際には、着火剤の使用をオススメします。
固形タイプの着火剤は、直接火をつけることができるため便利です。また、ジェル状の着火剤は炭や薪に塗布して使うタイプで、一定の範囲に火を広げるのに適しています。
新聞紙などの日用品で代用することも可能ですが、着火剤のほうが安全で簡単に火起こしをすることができます。
火おこし機
火起こし機は筒状になっており、中に炭を入れて使用し、その設計により空気が下から上に向かって流れることで、火を簡単に起こすことができます。
火起こし器の素晴らしい点は、着火剤に火をつけ、それを器の底に置いて炭を入れるだけで済むことです。
複雑な準備や技術がなくても、安定して早く火を起こすことができるので、キャンプ初心者は利用をオススメします。
ファイヤースターター
ファイヤースターターは、フェロセリウムやマグネシウムでできた金属の棒(ロッドやファイヤースチールとも呼ばれます)と、それを擦るためのストライカーが一組になっています。
ファイヤースターターを使用することで、ロッドをストライカーで擦るだけで火花が散り、燃えやすい材料に火をつけることができます。
ロッドが残っている限り、何度でも火を起こすことが可能で、燃料の枯渇を気にする必要はありません。
さらに、湿気や水に強く、低温環境でも機能するため、多少の天候の変化にも対応することができます。
耐熱グローブ
耐熱グローブは、直接火に触れることの多いキャンプでの作業を安全に行うために不可欠なアイテムです。
火のついた薪を移動させたり、熱した鉄板や直火で調理された食材を扱う際に、耐熱グローブがあれば手を守りながら作業を進めることができます。
耐熱グローブの利点は、ただ手を保護するだけでなく、その耐久性にもあります。高品質な耐熱グローブは、長期間にわたって繰り返し使用することができるため、一度の投資で長く使い続けることができます。
ただし油断は禁物で、焚き火の温度が1000度以上に達することもあるため、耐熱グローブを着用していても常に警戒心を持つようにしましょう。
薪ストーブと焚き火で使える薪の種類は違う?
テント内などで薪ストーブを楽しむ際に、焚き火で使った薪を使えるのか気になったことはありませんか?薪ストーブと焚き火のそれぞれには異なる特徴があるので、1回のキャンプでどちらも使用する事もあるかと思います。
しかし、それぞれに適している薪は異なるため、どちらにも同じ薪を使用すればよいというわけでありません。以下で、焚き火と薪ストーブに向いている薪の種類について説明します。
焚き火は、屋外で開放的に火を楽しむものです。そのため、以下のような特徴を持つ薪が適しています。
まず、火が付きやすく、燃え上がりやすい針葉樹がおすすめです。焚き始めや火力調整に役立ちます。そして、十分に乾燥している薪を選びましょう。湿度の高い薪は火が付きにくく、煙が多く出るためです。また、焚き火の規模に合わせて、適切な太さの薪を選びましょう。細すぎる薪はすぐに燃え尽きてしまい、太すぎる薪は燃えにくいです。
一方で、薪ストーブは、テント内など限られた空間で暖房や調理を楽しむものです。そのため、以下のような特徴を持つ薪が適しています。
まず、焚き火とは異なり、薪ストーブには火持ちが良く、安定した燃焼を持続する広葉樹が適しています。広葉樹を使うことで、屋内で長時間暖房として使用したり調理に使用したりできます。また、薪の太さに関しては、一般的に焚き火よりも太めの薪を使用するのがよいでしょう。
以上から、焚き火と薪ストーブでは異なる種類の薪を使うのが望ましいですが、焚き火で使った薪を薪ストーブで使用することは可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。
- 完全に乾燥していること
- 燃え残りがないか
- 薪の種類
焚き火で使った薪は、表面が乾燥していても内部が湿っている場合があります。薪ストーブで使う前に、十分に乾燥させてから使用しましょう。
また、焚き火で使った薪が完全に燃え尽きていない場合、薪ストーブの中で煙を出したり、煤が付着したりする可能性があります。燃え残りの少ない薪を選びましょう。
最後に、針葉樹は、薪ストーブで使用すると煙が多く出るため、広葉樹を選ぶのがおすすめです。
焚き火と薪ストーブでは、それぞれに適した薪があります。それぞれの薪の特徴を理解し、目的に合わせて適切な薪を選ぶことで、より快適なキャンプを楽しむことができます。
焚き火と薪ストーブで同じ薪を使用する場合は、上記の点に注意し、安全に使用しましょう。
薪に関するよくある質問
薪の種類によって燃焼時間は違う?
広葉樹の薪は火がつきにくいものの、一度着火すると長時間燃焼する性質があります。これは広葉樹の木材は一般的に密度が高く、燃焼により放出されるエネルギーが多いためです。
その結果、1束で約3~4時間の燃焼時間を期待することができます。
一方で、針葉樹の薪は火がつきやすく、着火しやすい特性を持っています。しかしその燃焼時間は短く、1束で約1~2時間の燃焼が見込まれます。
これは針葉樹の木材が広葉樹に比べて密度が低いことから、同じ量の薪でも素早く燃え尽きるためです。
焚き火での薪以外の燃料はある?
焚き火で使用することができる薪以外の燃料にはいくつかの種類があります。
・木質ペレット…木材の削りくずや粉を圧縮して作られた小さなペレットで、清潔で一定の品質を保ちやすいのが特徴です。燃焼時には比較的少ない煙が出ます。
・炭…BBQやグリルで一般的に使用される炭は、焚き火でも使用できます。炭は長時間にわたって一定の熱を提供し、火力を調整しやすいです。
・バイオマスブリケット…木材や植物の残渣を圧縮して作られた固形燃料で、環境にやさしく、持続可能な資源から作られることが多いです。
これらの代替燃料を使用する際には、周囲の自然環境や安全規則を尊重し、許可されている燃料のみを使用するようにしましょう。
1回の焚き火では薪はどれくらい使う?
焚き火を3~4時間持続させたい場合、針葉樹の薪1箱(3kg前後)と広葉樹の薪1束(7kg前後)を合わせたもので、基本的な要求を満たすことができるでしょう。
この量は、標準的なファミリー向け焚き火台での使用を想定した場合の目安です。
しかし、実際に必要となる薪の量は、焚き火の目的、焚き火をする季節やその時の気候、薪の種類や太さ、さらには焚き火台の特性や大きさによって変わります。
特に、冬場などの寒い季節に暖を取る目的で長時間の焚き火を楽しみたい場合は、基本量に加えて薪を3束ほど追加するなど、使用する時間や条件に応じて必要量を調整することが重要です。
薪の組み方にはそれぞれどのような特徴がありますか?
薪の組み方は大きく分けて3つあり、「井桁型」「並列型」「開き傘型」があります。
井桁型は空気の取り込みがしやすい構造であるため、中心から強い炎が上がります。
並列型は、火力の調整がしやすく、特に焚き火での調理を考えている方におすすめです。薪を枕木の上に並列に重ねることで、火力を調整しながら効率的に料理をすることができます。
開き傘型は、傘を開いたように薪を配置し、中央に燃えやすい細めの薪を置くことで、火は中央から外側へと徐々に広がります。火力は弱いですが、燃焼時間が長く、ゆっくりと焚き火を楽しみたい方に適しています。

ライター
Greenfield編集部
【自然と学び 遊ぶをつなぐ】
日本のアウトドア・レジャースポーツ産業の発展を促進する事を目的に掲げ記事を配信をするGreenfield編集部。これからアウトドア・レジャースポーツにチャレンジする方、初級者から中級者の方々をサポートいたします。