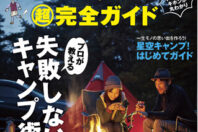滑落事故を防ぐポイント「滑落原因のトップは油断や気のゆるみ」

雪山で滑落事故が多いのは難所と呼ばれる尾根や急こう配の雪渓などですが、それ以外にも、「え!こんなところで滑落事故が起きたの?」と首をかしげたくなるような場所でよく事故が起きています。
ちょっとした油断や気のゆるみが命取りになるので、しっかりアイゼンの歯を地面に突き刺して、1歩1歩確かめながら歩くようにして下山するまで気を緩めないことが大切です。
非常食などを食べながら歩いていて転んで滑落するケースや、アウターを脱いだリ着たりしながら歩いていて転んで滑落するといったケースが多いようです。
用事がある時は必ず立ち止まってから済ませるようにしましょう。
また、道に迷って急いでしまったために滑落事故を起こすケースも多いようです。道に迷わないように注意することはもちろん、時間的にも体力的にも余裕のあるスケジュールで登山を計画することが大切です。
体力の消耗や精神的なあせりが事故につながることを覚えておきましょう。
滑落事故を防ぐポイント「やせた尾根での滑落事故」

北アルプスの燕岳や槍ヶ岳、剣岳(八峰・早月尾根)などは、やせた尾根が多く、場所によっては刃物のエッジのような尾根があります。
このような場所では慎重になっているので滑落事故自体は少ない状況ですが、雪庇といって強風で積雪が屋根の庇(ひさし)のようにせり出していることがあります。
雪庇のある尾根では、他の登山者のトレース(足跡)を頼りにするか、または、新雪が降り積もっている場合には、ひざ下にカウンというカバーをつけてラッセル(積雪を踏み固める)をしながら、足場を踏み固めて自分でトレース(道を作る)をしながら進みます。
また、このような雪山の場合には、2本のピッケルを両手に持って、しっかりと突き刺してバランスを崩さないよう支えとします。
ひざ下まで積雪がある場合にも、地面がどこにあるのかわからない状態なので、ラッセル(雪を踏み固めながら)をしながら自らトレース(通り道)を作って1歩1歩ゆっくりと進むようにしましょう。
急こう配の雪渓や雪の斜面ではキックステップが基本

急こう配の雪渓や雪の斜面では、キックステップによる上り下りが基本です。
キックステップとは、斜面に向かって張り付くようにして、アイゼンをはめた登山靴で雪渓や雪の斜面を2回ほど蹴って穴をあけて足場を作り、1歩ずつ登り、1歩ずつ降ります。
この時、ピッケルは、T字に交わった部分を持つセルフアレストグリップで持ち、雪の斜面に突き刺して滑落しないように固定してください。
岩場や鎖場、はしごを登る時と同じ「3点確保」(3点支持)の状態で登り降りします。
登山の基本「3点確保」(3点支持)
「3点確保」(3点支持)は雪山だけでなく夏山でも守らなくてはならない登山の基本です。
人には手が2本と足が2本あります。そのうち3本の手足は山に固定して、1本の手足だけを自由にして少しずつ移動するのが「3点確保」(3点支持)です。
はしごに登るとき、人は自然に「3点確保」(3点支持)を守って登り降りしています。登山でもそれを守るようにしましょう。
できるだけ木のある斜面を選ぶ
できるだけ木のある斜面を選んで登り降りすることも滑落事故を防ぐための大切なポイントです。
厳しい自然環境の中で生きる木々はとても頑丈です。細い枝でも何本か束ねると十分に安全な支持力が得られます。
できるだけ根本を持つことや、生きていることを確認することも大切です。
また、樹木が生えている場所は表層雪崩などが起きにくい場所でもあります。樹木に赤いリボンを結んで登山ルートの目印にしていることが多いのはそのためです。

ライター
Greenfield編集部
【自然と学び 遊ぶをつなぐ】
日本のアウトドア・レジャースポーツ産業の発展を促進する事を目的に掲げ記事を配信をするGreenfield編集部。これからアウトドア・レジャースポーツにチャレンジする方、初級者から中級者の方々をサポートいたします。