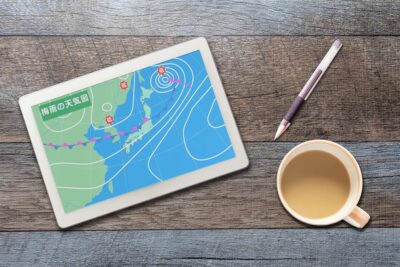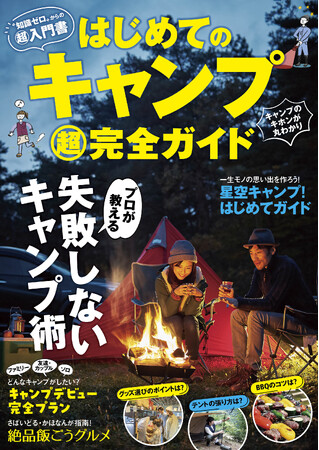ゴールデンエイジ期における習い事の注意点

ゴールデンエイジ期の習い事には注意しなければならない点がいくつか存在します。
まず、ゴールデンエイジ期の習い事における注意点をご紹介します。
できないことを怒らない
発達過程は、個人差がかなりあります。
「○○ちゃんはできたのに」や「なんで、できない?」など、子供の運動においてできないことがあっても、頭ごなしに怒ったり、人と比べたりしてはいけません。
怒っても子供はどうしら良いかわかりませんので、なんの解決にもならないのです。
怒るよりも、どうしたらできるようになるかを親子で考えると良いでしょう。
考える癖をつけてあげることの方が大切です。
過度な運動課題は与えない
子供に対して過度な運動課題は、負担でしかありません。
その年齢に適した運動課題をこなすことで、成功体験を積むことが大切です。
なによりも「運動が楽しい」「好きだ」と、思うように発達段階に応じた課題を与えましょう。
結果主義の習い事をさせない
本来、運動は楽しくするものです。
現代では勝利主義のスポーツが発展しすぎており、習い事をしているとコーチや監督の罵声が聞こえてきたりもします。
しかし、怖いから頑張るのでは長続きしませんし、精神衛生上もおすすめできません。
まずは、子供が楽しくスポーツや習い事ができるようにスクールやチームの選択が必要です。
ゴールデンエイジ期の怪我の実情

ゴールデンエイジ期に多いのが怪我です。
適切な運動をしていても怪我をする可能性はあります。
各時期で、とくに多くみられる事例をご紹介いたします。
プレゴールデンエイジ期
肘内障は好発年齢は2〜6歳で、急に子供の手をひっぱったり、ひねったときに生じます。
肘内障は、小さい子供に特徴的な障害です。
この時期の子供は、基本運動能力が未熟で遊んでいても親が目を離さずにはいられず、危険な行動を起こした際に怪我をすることが多いです。
※怪我発生の要因は、様々な因子が重なり合い生じるため、上記の内容に該当するから怪我をするわけではありません。
あくまで一つの要因です。
ゴールデンエイジ期
野球肘は好発年齢10〜16歳でボールの投げすぎや間違った投球方法により肘の内側を痛めます。
この時期は、基本運動機能を応用した動作の習得をすることができますが基本運動能力が未熟であったり、運動をやりすぎること・間違った運動方法によって怪我が発生します。
また、身体の発達が遅い子供ではボールをしっかりと握れないことから障害が発生することもあります。
※怪我発生の要因は、様々な因子が重なり合い生じるため、上記の内容に該当するから怪我をするわけではありません。あくまで一つの要因です。
ポストゴールデンエイジ期
腰椎分離症で小学生高学年から中学生低学年に発症します。
青少年の10%に好発し、スポーツをしている子供は一般の子供より3倍もの発生率となっています。
発生機序としては、過度な運動や上半身・下半身の柔軟性低下によって引き起こされるとされています。
この時期は、身長が急激に伸びる時期で骨の成長に筋肉の柔軟性が遅延することにより身体が硬くなります。
また反復した練習による疲労によっても柔軟性が欠如することもあり、コンディショニング不良によって引き起こされることが多いです。
※怪我発生の要因は、様々な因子が重なり合い生じるため、上記の内容に該当するから怪我をするわけではありません。あくまで一つの要因です。
各段階における適した習い事

各時期の適切な習い事の選び方や怪我についてご紹介してきました。
では、実際にどの時期に、どのような習い事をすればいいのかをここからご紹介いたします。
プレゴールデンエイジ
水泳や体操など全身を使った運動をさせることが適した時期です。
この時期は、基本動作能力の獲得が最重要となります。
ゴールデンエイジ期に運動スキルを身につけるための準備期間と考えましょう。
スキャモン曲線から考えられたプログラム、飛ぶ・走る・バランスをとる・投げる・リズムに乗って身体を動かすなどの運動要素を取り入れた運動を行うのが理想と言えます。
ゴールデンエイジ
プレゴールデンエイジ期に習得した基本運動能力を応用し、スポーツ動作の習得をしていく時期です。
この時期は、お子さんの興味がある・やりたいスポーツをやらせるのが一番でしょう。
注意点として、子供の発達には個人差があるため習得が遅いことや怪我をしてしまうことは多々あると思います。
時期がくればある程度、運動スキルを身につけることができるため焦らず見守りましょう。
ポストゴールデンエイジ
ゴールデンエイジ期に行っていた習い事を継続すると良い時期です。
身につけたスキルを反復することにより、さらに精度を高め、より進歩していきます。
そのため、慣れ親しんだ習い事を継続して行うのが望ましいのです。
注意点として、やりすぎや身体のケアを忘れず行うようにしましょう。
怪我の予防やスキルの向上にも繋がります。