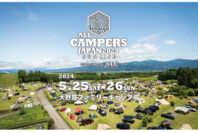春は虫が目覚める季節

日差しがあたたかくなり、山では雪解けがすすむ3月上旬頃、キャンプをするのにとても適した時期です。
この季節を二十四節季では「啓蟄」といいます。「啓」は「開く」、「蟄」は「虫などが土中に隠れ閉じこもる」という意味。
つまり、「冬ごもりしていた虫が土からでてくる」という意味合いで春の季語です。あたたかく過ごしやすい季節のはじまりですが、それは人も虫も同じ。
冬キャンプとはちがい、春キャンプをする際には、きちんと虫対策が必要になってきます。ここでは、春キャンプで注意が必要な虫類と、虫対策のポイントについて解説します。
春キャンプで注意したい虫とは

春はどのような虫に注意が必要なのでしょうか?春にキャンプ場で遭遇する可能性がある虫などを紹介します。
①ブユ・ブヨ
ブユまたはブヨとよばれるハエに似た虫で、黒っぽく丸い姿が特徴です。
人の皮膚を嚙みちぎって吸血し、その際毒液を注入します。噛まれた直後はあまりかゆみを感じませんが、翌日以降、激しいかゆみや痛みがあります。その際、患部が2~3倍に膨れ上がります。
リンパ肝炎などの重篤な症状になることもまれにあるので注意が必要です。
②マダニ
マダニは藪や野原などに生息するダニの一種で、通常は3㎜程度の大きさですが、吸血すると1cm近くまで膨れ上がります。マダニはくちばし状になった口を皮膚にさし、数時間かけて吸血します。
マダニで恐いのは、ツツガムシ症・ライム病・SFTS(重症熱性血小板減少症候群)といった重篤な症状を引き起こす恐れがあること。
マダニに吸血されたあとは、医療機関への受診が必要になります。
③チャドクガ
チャドクガは毒蛾の一種でツバキ・サザンカなどの低木に潜んでいます。
幼虫が茶類の葉っぱを食べるので茶毒蛾と呼ばれています。毛虫の毛針に触れると赤く腫れあがり非常にかゆくなります。
また、チャドクガの毛針は空気に乗ってあたりに散らばるので、触れなくても害があります。
④ムカデ
ムカデは虫ではありませんが、キャンプで遭遇することがある毒のある生き物です。
鋭い牙をもっており毒を注入します。噛まれると激痛が走り患部がはれ上がり、頭痛、発熱などを引き起こします。
テントや靴の中に入ることもあるので注意しましょう。
防止が重要!春キャンプでの虫よけポイント

ご紹介したようなキャンプで出会う可能性のある虫たち。できることなら会いたくないですよね。ここからは、春キャンプでできる虫よけポイントをご紹介します。
虫よけポイント①テントの場所・テントの工夫
春キャンプの時期は花木または新緑が美しい季節。
見上げたら満開の桜、そんなキャンプを満喫したいと、ついつい木のそばなどにテントを立ててしまいがちです。
しかし、木の周辺は毛虫などが落ちてくる可能性が多く、おすすめできません。対策としてタープなどをかけておくと、落ちてくる虫の害を防ぐことができます。
また、草むらなどにはマダニがいる可能性があります。高さのある草が生い茂る場所などは念のため避けた方がいいでしょう。
虫よけポイント②虫よけアイテムを使用する(スプレー・蚊取り線香・ランタン)
キャンプでは虫よけアイテムを使用するという方も多いと思います。
筆者もキャンプの時には虫よけ線香を持っていきます。虫よけ線香は蚊以外にもブユやアブも防ぐことができるので、季節を問わず持っていきましょう。
筆者はCDケースに虫よけ線香を入れて持っていきます。こうすると線香を折らずに持ち運べるのでおすすめです。
虫よけ線香は特大サイズで売られていることも多いので、少量を持ち運ぶには重宝しますよ。
コールマン アース極太 虫よけ線香
もうひとつ、虫よけアイテムとしてポピュラーなのが虫よけスプレーです。虫よけスプレーは予防できる虫の種類が豊富であること、手作りができることなどがあげられます。
蚊よけが一般的ですが、噛まれると重篤な症状を引き起こすマダニ予防のスプレーも各メーカーから販売されています。
あまり刺激の強い薬剤は使いたくないという方には、手作りスプレーがおすすめ。
エッセンシャルオイル(精油)と無水エタノール、精製水を混ぜ合わせることで簡単に作ることができ、虫の嫌う香りのエッセンシャルオイルを利用することで、虫の害を防止できます。
虫除けとして使用できるエッセンシャルオイルは下記のものがあります。
| 蚊 | ペパーミント シトロネラ レモングラス ゼラニウム |
| ブユ | ペパーミント シトロネラ ユーカリレモン レモングラス |
| マダニ | シトロネラ ユーカリレモン |
| アブ | ローズマリー |
また、オイルランタンをもっている方なら、虫よけができるオイルもあるので使用してみるのもおすすめです。
パラフィンオイル ランタン用 (KAVILA)
虫よけポイント③服装
虫よけには服装も重要なポイント。
肌の露出を極力避け、虫に噛まれたり刺されたりしないようにキャンプ場では長袖・長ズボンを着用し、首や足首など関節部分は露出しやすいので、おおうようにしましょう。
服の素材は明るい色のものを選ぶと、マダニなどに吸血されていた場合も、発見しやすいのでおすすめです。
また、アウトドアファッションには、素材自体に虫がつきづらい効果のある素材を使用したものがあります。これらのファッションやコーデを工夫して虫の害を防ぎましょう。
フォックスファイヤー 【防虫】【スコーロン】 SCコードレーン シャツ
虫に刺された!処置方法とやってはいけないこと

虫に刺されたら、ブヨやアブなどからさらに刺される可能性があるので、すぐにその場を離れましょう。
チャドクガなどは周囲に毒毛針が空気に乗って散らばるので、二重に被害を負う恐れがあります。ここでは処置方法と、やってはいけないことについて説明します。
虫に刺された・噛まれた時の処置
ブユ・チャドクガは毒針・毒液などを抜く
ブユなどに刺された場合は、患部を水で洗い流し毒を抜きます。チャドクガの場合はテープなどをつかって毒針を抜きましょう。
マダニ・ムカデなどの処置について
マダニに吸血されていることに気が付いたら、マダニの体を無理に引っ張ると、頭部だけがのこって埋没。さらに抜きづらくなってしまいます。
ピンセット等で口の部分をもって引き抜くか、難しい場合は医療機関にいきましょう。
ムカデに噛まれた場合は「毒を吸わない・冷やさない・温めない」ようにしてください。この3つはやってしまいがちですが、ムカデに噛まれたときは逆効果ですので注意しましょう。
ムカデの毒は40℃以下で活性化します。そのため、ムカデに噛まれた場合は42℃程度のやや高めのお湯で洗い流しましょう。
虫に刺された・噛まれた時やってはいけないこと
基本手には掻きむしることは虫の害にあった場合はNG行為です。毒の種類によっては、かゆみを抑える冷やす行為が逆効果になる場合もあるので注意しましょう。
ここでは、虫に噛まれた刺されたときにやってはいけないことをまとめました。
| ブユ・ブヨ | 搔きむしる・あたためる(かゆみがひろがる) |
| マダニ | 掻きむしる(感染症を引き起こすおそれ)・無理にひき剥がす |
| チャドクガ | 掻きむしる・あたためる(かゆみがひろがる) |
| ムカデ | 掻きむしる・毒を吸いだす。冷やす(ぬるま湯もNG) |
また、症状が重い場合はすみやかに医療機関にいきましょう。また、近年マダニによる感染症が増加傾向にあるようです。厚生労働省からも注意喚起が出されていますので注意が必要です。

ライター
Greenfield編集部
【自然と学び 遊ぶをつなぐ】
日本のアウトドア・レジャースポーツ産業の発展を促進する事を目的に掲げ記事を配信をするGreenfield編集部。これからアウトドア・レジャースポーツにチャレンジする方、初級者から中級者の方々をサポートいたします。