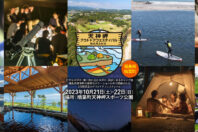そもそも天気の種類とは?

「明日は雨らしいよ。」天気はあいさつも含めて日常会話の話題として大変ポピュラーです。
しかし、何気なく言っている「晴れ」や「雨」「曇り」などの天気には、いったいどのような種類があり、そもそもどんな状態を指しているのでしょうか?
天気の種類は15種類
天気とは、気象庁の用語定義によると「気温、湿度、風、雲量、視程、雨、雪、雷などの気象に関係する要素を総合した大気の状態」となっています。
この天気について、気象庁では国内の天気として15種類に分類し、定義しています。
それは以下の15種類です。
- 快晴
- 晴れ
- 薄曇り
- 曇り
- 煙霧
- 砂じんあらし
- 地ふぶき
- 霧
- 霧雨
- 雨
- みぞれ
- 雪
- あられ
- ひょう
- 雷
しかし、晴れていても雨が降っている、みぞれ混じりの雨など、同時に複数の現象が現れることもあります。このような場合は、記した順番の後ろの方が採用されます。
つまり、晴れていても雨が降っている場合の天気は雨、みぞれ混じりの雨はみぞれとなります。なお、国際的に定められている天気の種類は、96種類もの数に上っています。
天気は西から変わっていく

「天気は西からやってくる」と昔から言われていますが、このことは皆さんも経験的に理解しているのではないでしょうか。
理由はきわめてシンプル
それは日本の上空を吹いている偏西風(強い西風)に沿って、高気圧や低気圧が西から東へと移動してくるからです。そのスピードはなかには例外もありますが、だいたい時速30〜40kmほど。
つまり1日で700〜1000kmの距離を進むことになります。この距離は天気図における経度線ほぼ1本分。高気圧や低気圧は1日で経度線1本分東に進むと覚えておくと、自分でそれらの位置を予想するときに役立つ知識です。
雲についての基礎知識

雲は天気のメインキャラクターです。雲が陽射しを遮り、雨や雪を生み出します。また、種類が大変多く、その種類や状態から天気に関するさまざまな情報を読み取ることができます。
雨雲と十種雲形
天気において誰でも最も気になる雲の種類は、やはり雨雲でしょう。日常生活での必須知識と言えます。
この雨雲を含めて、雲の種類は発達方向や形状、発生する高度などの違いによって、十種雲形として分類されています。
発達方向が垂直方向の雲を積雲、水平方向の雲を層雲に分類され、また高度によって巻層雲、高層雲、中層雲、下層雲と4段階に分けられますが、最終的には次の10種類となっています。
- 巻雲(すじぐも とも言う、以下同じ)
- 巻積雲(うろこぐも)
- 巻層雲(うすぐも)
- 高積雲(ひつじぐも)
- 高層雲(おぼろぐも)
- 乱層雲(あまぐも)
- 層積雲(うねぐも)
- 層雲(きりぐも)
- 積雲(わたぐも)
- 積乱雲(にゅうどうぐも)
この10種類の雲のなかで、雨を降らせるのは「乱」のつく雲と言われ、激しい雨をもたらし、時には雷を発生させるおなじみの積乱雲と、通称ですがそのものズバリ「あまぐも」と呼ばれている乱層雲がこれにあたります。
それ以外には、きりぐもの通称を持つ層雲が、霧雨を降らせる場合があります。低いところに発生する積雲も、沖縄など南国ではにわか雨を降らせることもあるため、これを含めて雨雲と覚えてもいいでしょう。
雲と霧、そしてもやの違い

雲は、大気中の水分が冷やされて固まり、小さな水や氷の粒子となって浮かぶものです。
それと同じように水分が粒子となって大気中に広がっているものに「霧」、さらに「もや」と呼ばれるものもありますが、この「霧」と「もや」は雲とどのように違うのでしょうか?
発生のプロセスによって名称が変わる
結論を述べるとこの霧と雲は同じものです。空に浮いているものが「雲」で、地上に接している時に、そのなかにいれば「霧」となります。そのため、霧が発生している場所を遠くから見ると雲に見えます。
ただし、この両者は発生するプロセスが異なります。上昇気流によって冷やされてできるのが「雲」で、湿った空気が上昇せずに冷やされて結晶化するのが「霧」なのです。
なお、霧ともやは同じものですが、視程(見透せる距離のこと)が1km未満の場合を「霧」、それ以上の時を「もや」と呼んで区別されています。
降水確率とは

天気予報が伝えてくれる情報のなかには、確率で示されているものがあります。その代表が降水確率です。この確率の意味は、誤解されていることが多いため、正しく把握しておきましょう。
降水確率は降水量とは無関係
その誤解とは、たとえば「確率が高いほど大雨になる」「0%だと雨が降らない」「50%だから1日の半分は雨が降る」「50%だからこのエリアの半分は雨が降る」などです。
降水確率は降水量とは無関係です。また、0%とは0.5%未満のことなので雨が降らないということではありません。さらに時間やエリアについてを指しているわけでもありません。
降水確率というのは1mm以上の雨や雪が降る確率のことです。降水確率30%とは、30%という予報を100回発出したときに、およそ30回は1mm以上の雨や雪が降るという意味になります。
1mmの雨というのはかなりしっかり降る雨で、雪ではうっすら積もっても不思議ではない量です。このように降水確率は、予報というよりも指針の類の情報のため、その意味を確実に理解して利用しましょう。

ライター
Greenfield編集部
【自然と学び 遊ぶをつなぐ】
日本のアウトドア・レジャースポーツ産業の発展を促進する事を目的に掲げ記事を配信をするGreenfield編集部。これからアウトドア・レジャースポーツにチャレンジする方、初級者から中級者の方々をサポートいたします。