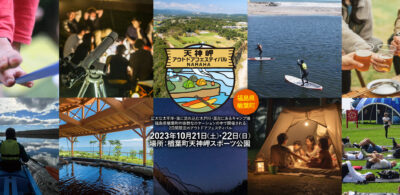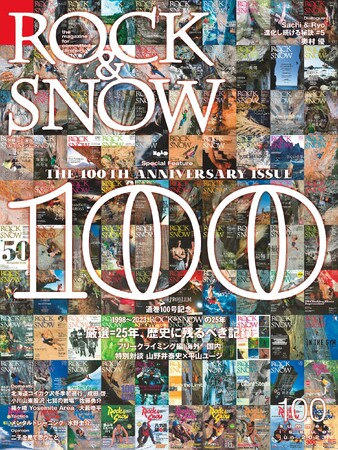ポイント① 種類とロープ径
クライミングロープは、伸縮性のあるロープでダイナミックロープといい、シングル、ダブル、ツインの3種類があります。
この3つのロープの大きな違いは、使い方とロープの太さ(ロープ径)。
シングルは1本で使うため、8.9〜11㎜と3種類のなかで一番太く、クライミングジムや直線的なルートのクライミングに使われます。
ダブルロープは、クライミングのなかでとくにハードだと言われるアルパインクライミングやアイスクライミングに使われる方法です。
2本のロープを別々のプロテクションにかけて安全確保をする方法のため、ロープ自体はシングルよりも細めの8㎜〜の径のものになります。
ツインロープと言うのは、2本のロープをシングルのように使う方法で、ロープ径は3種類のなかで一番細く7.4〜8㎜でとても軽いです。
このロープは、アイスフォールや海外の岩場といった直線的なクライミングに使われるのですが、使う場所が限定されるため日本ではあまり使われない方法です。
一般的なクライミングには、シングルロープが使われることが多く、初心者には10㎜以上のロープが手との接触面積が大きくビレイしやすいのでおすすめです。
また9.5㎜前後の細めのロープは、軽量なので中級者以上が好んで選ぶタイプ。
しかし、10㎜にくらべて接触面積が少ないので、握りにくいなどのデメリットもあります。
ポイント② UIAA耐墜落回数や伸長率など強度
クライミング用のロープは、その使用の目的上、安全基準についても明記されてます。
どんな物があるかというと、UIAA耐墜落回数、衝撃荷重、伸び率など。
耐墜落回数というのは、ロープの耐久性と強度を表す数字で、値が高いほど良いとされます。
そして衝撃荷重というのは、墜落したときに体に受ける衝撃の度数を表したもので、これは値が低いほど良いのです。
伸び率は、クライミング用のロープの特徴の伸縮性です。
これは墜落したときに伸縮性があると、その衝撃も低くなるためで、伸び率の値が大きければそれだけよく伸びるロープということです。
しかし、伸び率が良ければ、良いロープかと言うとそういうわけではありません。
伸び率が大きいと、墜落したときの距離も大きくなるので、最適は7〜8%が扱いやすいと言われています。
ポイント③ 撥水や防水加工の有無
クライミングロープと言うのは、すべてが撥水や防水加工してあるわけではありません。
たとえばクライミングジムで使う場合は、こういった加工がなくても大丈夫。
しかし、岩場など野外で使う場合は、撥水や防水加工をしてあるタイプが良いです。
雨などもありますが、山は数日前に雨や雪が降った場合、数日では完全に地面が乾かない可能性があるので、その状態でロープを使うと汚れます。
さらに、濡れたロープは伸び率が変わってきたり、強度も落ちるなどリスクが上がるためです。
そのため、岩場などに使う場合は、撥水や防水加工などコーティングがしてあるロープが良いでしょう。
初心者にはちょっと太めのロープがおすすめ
Petzl(ペツル)R32A マンボ10.1㎜
1963年創業のペツルはフランスの会社で、元々はヘッドランプを製造していました。
そこからクライミングギア、高所作業用品や、レスキュー用具などをつくるメーカーになり、世界的にも機能的で、テクノロジーを駆使した製品づくりには定評があります。
マンボウォールは、10.1㎜ と接触面積が大きいので操作性が良く、ロープ技術を習得中の人には扱いやすいのがポイントです。
耐墜落回数(落下率1.77)7回
衝撃荷重8.5KN
伸び率(静荷重)8.5%
Edelweiss(エーデルワイス) O-Flex 10.2㎜
エーデルワイスはフランスのロープメーカーで、1790年創業ということですでに220年以上もこの業界を引っ張っている名門中の名門です。
1900年代から登山用ロープの本格的な生産をはじめ、エーデルワイス社のSuper Everdryは国際山岳連盟が準拠した撥水加工の水準が最も高いと認められ、トップランクのロープとの評価を受けているメーカーです。
エーデルワイスのオーフレックスは、2009年のドイツのクライミング雑誌が発表した各メーカーのロープテストでも高評価を受けたロープで、ビレイデバイスとの相性やクリップのしやすさなどの面でも好評を得ました。
耐久性はもちろん、特殊なラウンドコア構造になっているので、キンクがしにくく操作性も良いです。
耐墜落回数8回
衝撃荷重8.2KN
伸び率(静荷重)9.5%