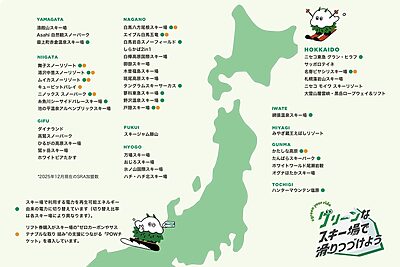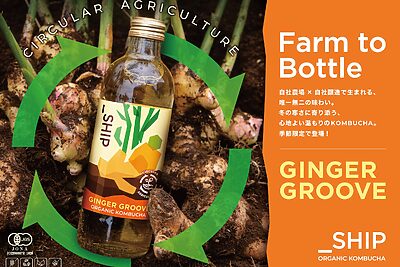家庭にひとつあると大活躍するヘチマたわし、実は簡単につくれます。特別な道具も複雑な手順も必要ありません。ヘチマ1本あれば、意外なほど手軽に始められる、大人も子どもも楽しめるやさしい手仕事です。この記事では、初心者でも安心して取り組める「自然乾燥」と「煮て作る」2つの方法を紹介。さらに、収穫のタイミングや乾燥のコツ、気をつけたいポイントもあわせてお届けします。自然素材の心地よさを感じながら、手仕事を楽しみませんか?
ヘチマたわしとは?

ヘチマたわしは、ヘチマの実を乾燥させて作る自然素材のたわしです。食器洗いやお風呂掃除など、日常のあらゆる「洗う」シーンで活躍してくれます。繊維がしっかりしたヘチマたわしは、丈夫で耐久性があります。一方で、水を含むと驚くほどやわらかくなり、自然素材ならではのやさしい使い心地を感じられるのが魅力です。
肌にも環境にもやさしく、使い終わったあとは土に還るので、ごみを減らすゼロウェイストな暮らしにもつながります。
市販のものもありますが、ヘチマの栽培からたわしの加工まで、自宅でも簡単に挑戦できます。自分で作れば、大きさや形も自由自在。暮らしに自然と溶け込む、自分だけのヘチマたわしを楽しめますよ。
方法1.置いておくだけ!自然乾燥のヘチマたわし作り

収穫に適した完熟ヘチマ。茶色くなると中の繊維もしっかりしています。
ヘチマたわしを作る方法はいくつかありますが、「できるだけ手間をかけずに、自然の力に任せたい」という人には、自然乾燥がおすすめです。収穫や乾燥のポイントを掴むことで、特別な道具もスキルも不要。小さな子どもでも簡単にできる方法です。
収穫のタイミング
自然乾燥させる場合の収穫に適したタイミングは、完熟した後に外皮が茶色くなり、軽く叩くとカラカラと乾いた音がする頃です。実を持ち上げると、ずっしりしていた重みが抜け、軽く感じるようになります。
収穫が早すぎると水分が多く、乾燥中に中が傷んでしまったり、繊維がやわらかくてちぎれやすくなったりすることも。 「しっかり乾いてきて水分が抜け、軽くなってきたころ」をひとつの目安に、完熟のサインを見極めて収穫しましょう。
手順
- 収穫後、自然乾燥させる
収穫したら、まずは風通しの良い日陰で1〜2週間ほど自然乾燥させます。置いておくだけで、皮がさらに硬く乾き、むきやすくなります。雨の当たらない軒下や日除けのあるベランダなどがおすすめです。 - 皮をむく
乾燥してパリパリになった外皮に、手で割れ目を入れるか、ハサミ・ナイフで軽く切り込みを入れて丁寧にはがします。中から現れる繊維が、ヘチマたわしの素材です。 - 種を取り除く
中にはたくさんの種が詰まっています。軽く振るだけで簡単に出てきますが、うまく出ない時は、流水を使って丁寧にかき出しましょう。ヘチマを縦半分にカットすると、奥の種もきれいに取り出せます。取り出した種は、来年のヘチマ栽培用に。種もしっかり乾燥させて保管しておきましょう。 - 水気を切って干す
種を取り除いたあとは、布巾やキッチンペーパーで水気を軽く拭き取り、通気性の良い場所でさらに1〜2週間ほどしっかり乾燥させます。湿気がこもるとカビの原因になるため、時々向きを変えて乾かしましょう。しっかり乾燥したら、ヘチマたわしのできあがりです。乾燥後は、高温多湿を避けて長期保存ができます。
方法2.煮るだけ簡単!短時間でヘチマたわし作り

まだ黄色っぽいヘチマも煮て作る方法であれば、手軽に加工できます。
「できれば早く完成させたい」「収穫後のカビが心配」という人には、煮沸による方法がおすすめです。作業はシンプルで、自宅にある道具を活用して手軽に挑戦できますよ。
収穫のタイミング
自然乾燥と同様に、収穫に適したタイミングは、実が完熟して外皮が茶色くなり、手に取ったときに軽く感じる頃です。しっかり熟したヘチマは繊維がほどよく締まり、たわしにぴったりの硬さになるため、加工もしやすくなります。
万が一、少し早めに収穫してしまっても、「煮て作る方法」なら傷む前に加工できるので安心です。果肉が多く残っていると、そのぶん取り除く手間はかかりますが、繊維がしっかりしていれば、十分立派なたわしになりますよ。
用意する道具
- 完熟したヘチマ
- まな板
- 包丁
- 大きめの鍋
- 落とし蓋(もしくは鍋に入るサイズのお皿)
- ざる
- ボウル
- 菜箸・トング
手順
- 完熟したヘチマを包丁で切り、種を取る
完熟したヘチマを鍋に入る大きさにカットします。流水で洗い流し、中の種を取り出しましょう。全て綺麗に取らなくても大丈夫です。 - 鍋で煮る(10〜15分)
大きめの鍋にお湯を沸かし、ヘチマを入れて煮ます。ヘチマが浮いてきてしまうので、落とし蓋やお皿を乗せておくのがおすすめです。途中で向きを替えながら均等に火を通しましょう。 - 流水で洗う
茹で終わった後のヘチマは、トングや菜箸で取り出します。熱いのでやけどには十分注意しましょう。
ある程度冷めたところで、流水でやさしくもみ洗いし、皮や種、ぬめりを取り除きます。簡単に皮がはがせるので、小さな子どもでも取り組めますよ。 - 水気をしっかり切る
布巾などで包んで水分を軽く押さえたあと、風通しの良い場所で1〜2週間ほど、しっかり乾燥させましょう。 - カット・成形して完成
使いやすい大きさにカットし、好みに合わせて形を整えて完成です。乾燥後はすぐに使えますが、高温多湿を避ければ、長期保管が可能です。
失敗しないコツは?手作りヘチマたわしのポイント

若い実を収穫したら食用に。みずみずしくておいしいですよ。
ヘチマたわし作りはシンプルな手仕事ですが、ちょっとした工夫で仕上がりがぐんと良くなります。失敗を防ぐためのポイントを押さえて、気軽に楽しく取り組みましょう。
収穫時期を見極める
未熟なヘチマの実は、加工しにくかったり、乾燥中に傷んでしまったりすることもあります。完熟をしっかり見極めてから収穫することが、成功の鍵です。
焦らずじっくり育ててから収穫しましょう。もし若い実を収穫してしまった場合は、食用としておいしくいただく、もしくは「煮て作る」方法で早めに加工しておくといいでしょう。
保管前によく乾燥させる
乾燥が不十分なまま保存してしまうと、ヘチマたわしにカビが発生する原因になります。加工後のヘチマを干すときは、湿気がこもらない風通しの良い場所を選び、なるべく直射日光を避けて干すのがおすすめです。
カゴやザルを使うと通気性が高まり、均一に乾かしやすくなります。干しかごを利用するのも良い方法です。また、果肉が残っているとカビが発生しやすくなるため、加工時に必ず取り除くようにしましょう。
最初は1本から気軽に
「初めての挑戦でうまくいくか心配」という人は、練習のつもりで1本だけ作ってみるのがおすすめです。手順を覚えたら、次は何本かまとめて作ってストック用にしてもいいですね。
実際にやってみると、シンプルな作業ながら達成感もあり、ものづくりの楽しさを味わえます。無理のないペースで、日々の暮らしにちょっとした手仕事を取り入れてみてくださいね。
ほんの少し手を動かし、工夫を加えることで、暮らしに心地よいひとときを取り入れてみませんか。環境にやさしいヘチマたわしは、日々の「洗う」をやさしく彩ってくれるはずです。

ライター
AYA
静岡県出身。海と山に囲まれた自然豊かな環境で育ち、結婚後に、タイ・バンコクへ移住。病気がきっかけで、ヴィーガンのライフスタイルに目覚める。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら、人と環境にやさしいサステナブルな暮らしを実践中。自身の経験をもとに、ヴィーガン、環境問題、SDGsについて情報を発信している。