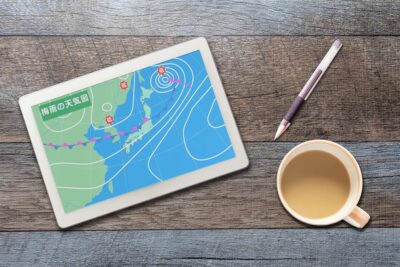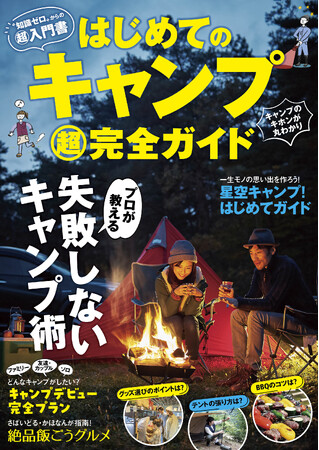子どもと野外へ出かけるのに最適な季節。しかし、草むらで遊んでいる間にマダニに刺される可能性があることを知っていますか?マダニは吸血しながら感染症を媒介する厄介者。特に、命に関わる感染症(SFTS:重症熱性血小板減少症候群)には注意が必要です。この記事では、マダニの生態と感染症リスク、そしてマダニから子どもを守るための対策について紹介します。正しい知識を知り、安心してアウトドアを楽しみましょう。
マダニとはどんな生きもの?

マダニは節足動物の仲間で、クモやサソリに近い生き物です。クモの仲間のうち「ダニ目」に属し、体が小さく頭と胴の区別がはっきりしないという特徴をもちます。世界中で800種以上が知られており、そのうち日本に生息するのは47種です。
マダニ対策を適切に行うために、生態を知っておきましょう。
マダニの生態

マダニは森林や草むらなどに生息し、哺乳類や鳥類などの血を吸う生きものです。吸血前の成虫は2~4㎜ほどですが、吸血後は1cmくらいに膨らむこともあります。
マダニの卵は乾燥に弱いので、草むらの中など直射日光が当たらず湿度が保たれている環境、例えば落ち葉の下や植物の根元に産みつけられます。成長したメスのマダニは吸血後に交尾し産卵しますが、その数はなんと数千個。多くが生き残れないため、多数産むことで生存率を確保する戦略です。
数週間〜数か月後に卵から幼虫がかえると、幼ダニ、若ダニ、成ダニの各ステージで1回以上吸血し成長します。人以外に、野ネズミ、野ウサギ、シカ、イノシシなどの野生動物や、ネコ、散歩中のイヌなども吸血の対象です。
マダニの主な活動期間は春から秋(3月〜11月)ですが、冬でも活動する種類もいます。個人宅の庭や畑、草に覆われた道端など意外に身近な場所にも生息しており、シカやイノシシなど野生生物が多く出現する環境では特に注意が必要です。
感染症との関係
マダニは、日本紅斑熱、ライム病、つつが虫病、ダニ媒介脳炎などの感染症を媒介します。なかでも重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、国内での致死率は20〜30%と高いため特に注意が呼びかけられている感染症。潜伏期間は通常6〜14日程度で、発症すると発熱、消化器症状、血小板減少、白血球減少などが生じます。
SFTSウイルスによる感染が日本で初めて報告されたのは2012年で、現時点で特異的な治療法や予防ワクチンがなく、対処療法が中心です。国内ではフタトゲチマダニ、タカサゴキララマダニなどがSFTSの感染に関与しており、マダニ→ペット→飼い主という感染も確認されています。
2021年以降は西日本を中心に毎年100名を超える患者が報告されており、一人ひとりのマダニ対策が重要となっています。
アウトドアで気を付けるべきポイント

アウトドアでは、マダニが入り込まない服装を選び、マダニの好む環境をなるべく避けることが重要です。また、万一、マダニが付着していても、着替えや入浴のタイミングで取り除くよう気を付けましょう。
特に子どもは全身で草むらに入り込んだり、地面に転がったりするのでリスクが高まります。ここでは、子どもとのアウトドアで気を付けるべきポイントについて確認しましょう。
マダニを寄せつけない服装
長袖・長ズボンで肌の露出を少なくするのが基本です。まず、頭には帽子。襟付きのシャツを着るかタオルを巻いて首を保護し、シャツの裾はズボンの中に入れましょう。さらに、ズボンの裾に靴下を被せ、サンダルではなく足を完全に覆う靴を履きます。
マダニにも効く虫よけ剤を服にスプレーするのも効果的です。国内ではディートやイカリジンを有効成分とする製品が販売されています。ディートは「6か月未満には使用しない」「12歳未満には1日3回まで」などの制限がありますが、イカリジンは小さい子どもにも使用でき、6時間以上効力が続くためお勧めです。
マダニが居そうな場所を知る

ニホンジカの足跡
わずか数㎜のマダニを野外で見つけることは難しいため、マダニが居そうな場所を避けるしかありません。まず、湿った環境の草むらはマダニが生息している可能性の高いスポットです。
さらに、野生動物が利用した痕跡のある場所、例えばイノシシが転がった「ぬたば」※やシカの足跡があるような場所は、野生生物の体から離脱したマダニがいるかもしれません。
このような場所に近寄らなければ安心ですが、どうしても遊びたい場合は念入りに虫よけ剤をスプレーし、長時間座り込んだりしないよう気を付けましょう。
※イノシシやシカなどの野生動物が、泥の中で体を転げ回って泥を浴びる場所のこと。体についた寄生虫や汚れを落としたり、体温調節をしたりするための行動と考えられている
帰宅後も油断しない
マダニを家の中に持ち込まないよう、帰ってからの行動が大切です。家に入る前に上着や鞄の汚れを払い、気になる汚れはガムテープで取り除いて、洗えるものはすぐに洗濯しましょう。
帰宅後すぐに、シャワーやお風呂でさっぱりするのがお勧めです。本人が見えにくい部分を中心に、大人が丁寧に確認してあげましょう。特に、首、耳、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏などがポイントです。
また、小さい子どもの場合は頭をうまく洗えず、髪の中に潜り込んだ虫を洗い流せないかもしれません。アウトドアを楽しんだあとは、髪で見えない頭皮も気にかけてあげてください。
マダニに刺されたら?

吸血したマダニは米粒大で黒っぽく、肌にしっかりくっついているので、「ほくろ」か「おでき」と見間違えるかもしれません。マダニに刺されたときには気が付かず、数日間吸血し続けたあとにマダニの体がパンパンに膨れ上がって、初めて認識されることが多いようです。
刺されたことに気づいた場合、基本的には皮膚科などで除去してもらいます。吸血中のマダニを無理に取り除こうとすると、マダニの体液が逆流し病原体が皮膚内に入りやすくなるほか、マダニの口器が皮膚の中に残ると化膿することがあるからです。また、吸着後3日以上が経過すると、マダニの口器が皮膚と固く接着し除去が難しくなるため、受診が必要になります。
しかし吸着後早い段階では、病院にどうしても行けない事情がある場合、推奨はされませんが自分で除去する方法もあります。先の尖ったピンセットなどでマダニの口器の部分を摘んでゆっくり引き抜くと、うまく除去できることが多いようです。腹部を指で摘まむと、マダニの体液成分が皮膚内に流入しやすくなるので避けましょう。
なお、数週間は体調の変化に注意し、発熱等の症状が出た場合にはすぐに医療機関を受診してマダニに刺されたことを伝えましょう。
参考
マダニ対策、今できること|国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A|厚生労働省
マダニ類に刺されたらどうすればよいですか?|公益社団法人 日本皮膚科学会

ライター
曽我部倫子
東京都在住。1級子ども環境管理士と保育士の資格をもち、小さなお子さんや保護者を対象に、自然に直接触れる体験を提供している。
子ども × 環境教育の活動経歴は20年ほど。谷津田の保全に関わり、生きもの探しが大好き。また、Webライターとして環境問題やSDGs、GXなどをテーマに執筆している。三姉妹の母。