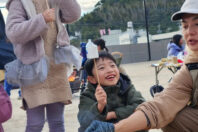パークビルドは園児の楽しみを増やすため

ー施設内のパークは自らの手で制作したDIYパークとのことですが、なぜ自らの手で作ろうと思ったのですか?
パート1でも少しお話しましたが、最初にここの施設を買い取った時は、すでにパークの基礎工事は完了していて、ミニランプとそこから続くウェーブ、奥にあるフラットバンクはできていたんです。
でも施工業者がスケートボードの知識がない人だったのか、フラットバンクのアプローチ部分が急すぎるという設計ミスがあって、かなりの上級者でないと使えるものではありませんせんでした。
そのようなセクション(障害物)だったら、当然プリスクールに入るような子どもに使いこなせるわけがありません。だから最初の頃は皆ミニランプしか使っていませんでした。
でもその時に他にも面白いセクションがあったら、子どもたちのやれることややりたいことが増えて、スケートボードの魅力にもっと触れることができると思ったので、自らの手でセクションを造ろうと思ったんです。
そこで、まずは奥のフラットバンクの入り口にアールを作って斜面をなだらかにすることで、アプローチしやすくするところか始めました。
そうしたらすごくやりやすくなって、子どもたちもどんどんと新しいことにトライしてくれるようになったので、それならこっちも造ろう、あっちも造ろうという形でどんどんと想像が膨らんでいったんです。
設計から施工まで全てひとり

ーそこから発展して今はすごく手の込んだパークに仕上がっていますが、設計・施工に関しての専門的知識はどのようにして身につけたのですか?
じつはココを作る前に、同じ田原市にあるチルアウトというサーフショップでD.I.Y.スケートパークの建設を手伝いながら学ばせてもらっていたんです。
そこのセクションのいくつかは自分一人で造ったんですよ。だからリアルタハラはその時に得た技術を活かして、設計から施工まで全て自分一人で行いました。
実際にチルアウトでD.I.Y. コンクリートパークを造ったことで、ココは少し長さが足りないなとか、ココは角度がちょっと緩すぎるなとか、そういう細かな部分を感覚で理解できたことが大きかったですね。
基本的にコンクリートパークはベースとなる土地に型を造って、そこにセメントを流し込んでいくんですが、その型造りに大いに役立ちました。
それと、流し込むセメントも、ほとんどは自分がホームセンターで買ってきて配合したものなんです。
そういったコンクリートやセメントの配合は一見難しそうに感じるかもしれませんが、今は全てインターネットで調べる事ができますし、英語ができれば調べ物ができる範囲も膨大になるので得られる情報量も全然違うんです。
極端な話をいえばアールの感覚や、フラットはこれくらいの距離があれば大丈夫だなとか、そういった細かな情報も得ることができるので、そういったところからコツコツと勉強していって、今のリアルタハラができ上がったんです。
オーリーができなくても楽しめるパーク

ーではどういう過程を経て今のパークになったのか教えていただけますか?
バンクの入口をなだらかにしたら、次にパーク全体をスムーズに回れるようにしたかったので、ミニランプの横にラウンドコーナーを造りました。
そうしたら入口をなだらかにしたバンクの方も同じようにコーナーを造れば、さらにパークをスムーズに回れて面白くなると思ったので、トンネル付きっていう一捻り加えたラウンドコーナーを足しました。
でもこの時点ではフラットには何もなかったので、墓石素材を埋め込んだカーブボックスと、レンガ素材のヒップを造ってバランスを整えたんです。
ーもうそこまでいったらパークビルドが止まらなくなりそうですね。笑
本当にその通りで、ミニランプの奥にぽっかりスペースができたので、次はそこに変形ボウルを入れようって事で、スコップを使って掘り起こすところからやったんです。これは完成まで1年3ヶ月もかかりました。笑
これが完成したのが2018年で、フラットバンクから続くラウンドしたコーナーの先にある脇のウェーブセクションもその頃です。これは型を作るのが大変でしたね。
そして奥にあるベンチのアールが2019年、さらに焚き火ができるランプとレンガウォールのセクションは2020年の夏に完成しました。
ー差し支えなければ制作期間と制作費を教えていただけますか? あとリアルタハラのパークを造る上でもっとも意識していることも教えてください。

制作期間に関しては、現在進行形で常にセクションを造り足してるからいつからいつまでっていうのはないですね。
でもスタートはプリスクールを始めてすぐの頃で2014年なので、かれこれ7年以上かけてコツコツと造り足し続けています。
だから製作費もその都度材料を買い足して造ってるので、合計でいくらかかっているのかは自分でもわかりません。でも全部自分でやると大変だけど想像以上に安く造れますよ。
あとパーク構成に関してなんですが、全てプリスクールに通う幼児が使うことを前提にして造るようにしています。
言い換えれば、脚力がなくてオーリーから何かに入るっていうことをしなくても楽しめるパークです。
でもそれだけではバリエーションが乏しくなってしまうので、中には高さは低いですがカーブボックスなどオーリーができなければ使えないセクションもあります。だからそこは可動式のバンクを脇につけたりしながら調整するようにしています。
自作セクションがSNSを通じて世界的な話題に

ー過去のスケートボードメディアでのパークの露出はありましたか?
instagramアカウントの @skatediyには何回か載せてもらってます。これは名前の通り世界各地にあるD.I.Y. スケートスポットを紹介しているアカウントなんですが、2019年に造ったベンチのアールセクションが世界的にも評判になりました。その投稿はハッシュタグ #myDIYisDRY で検索してもらえると見つけやすいと思います。
またskatediyはその投稿以外にも僕と娘の楓をいろいろとフィーチャーしてくれて、楓のD.I.Y.スポットツアーの案内映像なんかもいくつか出ているので、世界中のいろいろな人からコメントをもらうようにもなりました。
ーパークは一般の方の滑走も可能なのですか?
プリスクール中はもちろん不可能ですが、それ以外の時間は事前に連絡をもらえれば可能です。基本的に平日は14時30分から日没まで、土日祝は不定期オープンなので事前に確認してもらった方が良いですね。
あとはパート2でもお話しましたが、月に1~2回ナイターデイを設けているので、その日は夜間も滑走可能です。
ただどの場合もオープンする場合は事前にinstagram(@realtahara) やfacebookで告知しているので、滑りたい人はチェックしてみてください。滑走料金は500円になります。あとパークの貸切に関しても応相談で対応しているので、気になる方は連絡をください。
ー過去にリアルタハラのスケートパークで何かイベントは開催しましたか?
コンテストは毎年開催していましたよ。取引先に協賛品を出してもらって、一般の方も参加できるようなものを企画していました。スキル別にミドルクラスとオープンクラスに分けつつ、その中にリアルタハラらしく保育園児クラスも入れたりといった形で。ちなみに保育園児クラスの参加者ほとんどはリアルタハラの園児達です。そういった形で皆で楽しく滑っていたんですが、去年は皆さんご存知のコロナ禍で開催を見送らざるをえませんでした。今年はなんとか開催できたら良いなと思っています。
今後のスケートパーク運用プラン

ー今後このスケートパークをどのようにしていきたいと考えていますか?
コロナが落ち着いたらになってしまうかもしれませんが、イベントをもっと増やしていきたいですね。コンテストの開催もそうなんですが、ライブイベントなんかもできたら最高だなと思います。
じつはライブは以前にもやったことがあってかなり盛り上がったので、そういった方向性も良いなと思っています。
リアルタハラの近くには住宅がなく、あるのは畑と保育園くらいです。その保育園も夕方に閉まるので、それ以降は周囲に音で迷惑をかけることもないんです。
そうしてできることの幅を広げていけば、もっといろいろな人にリアルタハラのことを知ってもらえると思いますし、いろんな人が来てくれるのではないかと思っています。
ーではスケートパークのリニューアルや今後のセクション増設プランがあれば教えてください。
今一番やりたいのはミニランプの半分くらいの幅を30cmくらい高くすることですね。それだけでかなり面白くなると思いますよ。
あとは真ん中のフラットスペースに置いている赤いスラッピー用の縁石セクションを、パークの脇に移動して常設にしようと思っています。これくらいならそこまで時間をかけずにできるかなと思っています。
そうしたらその次はベンチのアールセクション横の空きスペースに、ゴマ擦りのような形状の小さいボウルを造りたいです。それで特大トランスファーしている姿を見てみたいですね。
あと、いつかはパークのメインスペースと、焚き火ランプスペースをコンクリートでくっつけて、自由にプッシュで回れるようにしたいです。
今までこれだけいろいろなコンクリートセクションを造ってきたので、もう中毒化していて常に何かしら造りたいって気分になってしまっているんですよね。笑
まあ半分自分の趣味も兼ねていることなので何年かかるかはわからないですが、マイペースに造り続けていって、これからもセクションは増やし続けていきますよ。
リアルタハラの未来像

ープリスクール全体としては今後どのようにしていきたいと考えていますか? 将来的な方向性も含めて教えてください。
特に規模を拡大するというようなこともなく、このままで継続してやっていきたいと思っています。
今は地域住民の方々も皆が理解してくれるようになって、ほぼ定員上限というところまで園児が入ってくれるようになりました。
なので今後もそこは維持しつつ、子どもたちのためにより良いイベントを企画したり、楽しい体験をたくさんしてもらえるような施設にしていきたいと思っています。
あとは自分自身、地域の田原市のI街づくりグループにも参加しているので、リアルタハラを拠点にスケートとサーフで町興しができるような動きも合わせてしていきたいですね。
プリスクールだけに収まることなく、そういった活動をして市内の公共スケートパーク建設につながれば、もっといろんな人が田原市とリアルタハラを知ってくれると思いますし、相乗効果でもっと盛り上がっていくと思っています。これからも自分にできることは精一杯やっていきますよ!
ーいろいろとありがとうございました。最後に現在幼児教育をされている親御さんにメッセージがあればお願いします。
僕は子ども達にいろんな経験をしてもらって、それで幅広い視野を持ってもらいたいという想いでリアルタハラを運営しています。そしてその経験は必ず子供達をより良い未来へ導いてくれると信じています。
なのでご両親にもそういう風に幅広い考えや視野を持ってもらって、既成概念に囚われない育て方をしてほしいなと思います。
自分はカナダという日本とは全く違う育児環境で育ちましたが、今や人生の半分を日本で過ごすまでになりました。
だから双方の文化を理解しているつもりですし、だからこそ幅広い視野を持って自分で選択することの重要さも身を以て経験してきました。そういう考えをリアルタハラでは伝えるようにしています。
もし興味がある方がいたら、ウチはいつもオープンなので、滑りに来るでも波乗りついででも良いので寄ってみてください。子ども達と一緒に楽しみましょう!


ライター
吉田 佳央
1982年生まれ。静岡県焼津市出身。高校生の頃に写真とスケートボードに出会い、双方に明け暮れる学生時代を過ごす。大学卒業後は写真スタジオ勤務を経たのち、2010年より当時国内最大の専門誌TRANSWORLD SKATEboarding JAPAN編集部に入社。約7年間にわたり専属カメラマン・編集・ライターをこなし、最前線のシーンの目撃者となる。2017年に独立後は日本スケートボード協会のオフィシャルカメラマンを務めている他、ハウツー本も監修。フォトグラファー兼ジャーナリストとして、ファッションやライフスタイル、広告等幅広いフィールドで撮影をこなしながら、スケートボードの魅力を広げ続けている。