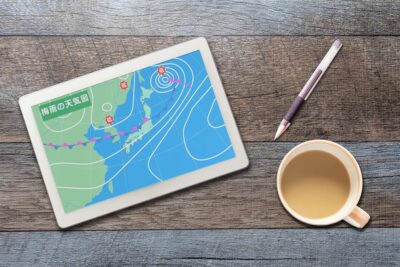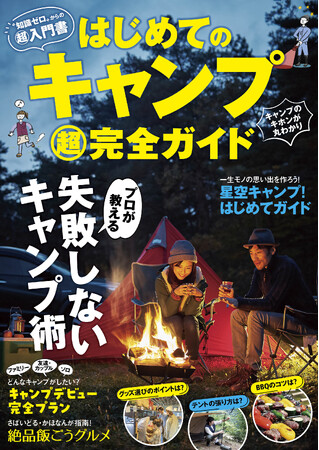空間認識能力について知る

空間認識(空間認知)能力とは、読んで字のごとく、空間を正しく認識できる能力のことです。
3次元空間上の物体の位置や形状・方向・大きさなどの状態や位置関係を素早く正確に把握する能力になります。
この能力によって、目の前に無いものを頭のなかで想像し、視覚的なイメージを形成することができます。
言葉だとむずかしいですが、地図で例えてみましょう。
カーナビゲーションが普及するまえ、まだ地図が紙でしかなかったときには地図を見ながら旅行したものです。
助手席の人が地図を見ながら、道を案内するかたちが定番でした。
地図を空間的にイメージして理解すること、これこそが空間認識能力というわけです。
ある研究によれば、この空間認識能力は男性に比べ女性の方が低いとされていますが、全ての男性が女性より高いということではありません。
場合によっては、女性の方が高いケースもあることも事実です。
空間認識能力が活用される場面

空間認識力は、どんな場面で活用されるのか?
ここでは、空間認識力がどんな場面で活用されているのかを身近できごとと、照らし合せてご説明していきたいと思います。
空間認識力とスポーツ
空間認識能力は、球技をはじめとしたスポーツ全般においてとても重要な能力です。
ある研究では、空間認識能力を測定するテストにおいて、スポーツ選手は一般の人と比べ高いスコアを獲得しています。
サッカー日本代表の監督を務めた手倉森誠氏は、それを裏付けるかのような話をされています。
「身長が高い選手がヘディング上手な選手というわけではなく、空間認識能力が高い選手ほど上手い選手である」と、話しています。
つまり、高速でかつ高難度の動きを求められるスポーツにおいて、空間認識能力がいかに重要かわかります。
空間認識力と日常生活場面
日常生活場面では、空間認識力が求められることが多くあります。
もしも、空間認識力が低いと交通事故にあう頻度が増加するのです。
これは、車と自らの距離感を誤解し事故にあうケースです。
信号のない横断歩道を渡る際、「車はまだ先にいるし渡っちゃえ」と、進んでしまうからです。
このように、空間認識能力は運動や日常生活を安全に過ごすためにもとても重要な能力なのです。
アウトドアで知る空間認識能力

空間認識能力を知るためには、なによりも多くの情報量が必要です。
屋内と屋外で比較すると、屋外の方が多くの情報を得ることができます。
自分に備わっている空間認識力を知るためには、屋外での遊びが有効的とされています。
屋外での遊びは、いろいろな情報を処理する能力が必要となります。
ここからは、アウトドアなどで知ることができる自らの空間認識能力についてご紹介いたします。
空間認識力と鬼ごっこ
鬼から逃げようと、3次元空間を自由自在に動きまわる鬼ごっこは、空間認識能力を知るための最適な屋外遊びです。
鬼との距離感や、どこにどうやって逃げれば捕まらないかを考えながら遊びます。
公園などでは障害物も多数あるため、その障害物にあたらないように鬼から逃げる方法を瞬時に判断し、即行動に移ことができれば空間認識能力が高いと言えます。
空間認識力とハイキング
山や谷などのハイキングを行うことで、空間認識力をはかることができます。
地形の形状や、安全に登るための方法を考えることで空間認識能力が活用されます。
また山頂から眺める景色を見ることで、どのような場所にどのような距離感で物体や山々が位置しているかを知ることができます。
空間認識力とパラグライダー
パラグライダーは、かなり高度な空間認識力を必要とします。
上空から地上までの距離感や、物体の位置関係の把握・着陸するのに最適な場所の判断、上空の風の程度など知るために空間認知能力が必要とされます。
パラグライダーを行うことで、上記のような内容を即座に判断する能力と空間認知能力を知ることができます。
空間認識力とダンス
団体で行うダンスで、空間認識能力を知ることができます。
たとえば、腕を前後左右に振っても手足がぶつからないか・踊っている際に隣の人にぶつからないかなどダンスにおいて、さまざまな空間認識能力を要求されます。