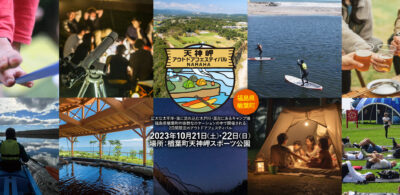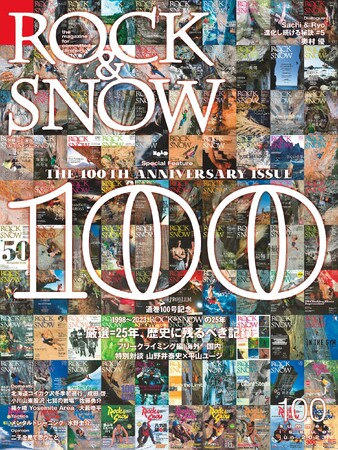チームスポーツが苦手な子ほどクライミングが上達する理由
チームスポーツが苦手という子は、集団に溶け込めないのではなく、集団でひとつの目標に向かう事に向いていないタイプです。もちろん人間は一人で生きていけませんので、常に集団に属して生きていきます。

社会には、家族、学校、地域、など、たくさんの集団があります。しかし、その集団というのは個人の選択をある程度許容したものです。家族は子供にとって安らぎの場であり、選択の自由があります。
学校も休み時間に遊ぶ友達を選択できます。しかし、スポーツの世界に限っては、チームの成果が最も重要になります。
プレイヤーが全員好きな事をしてしまっては、どんなにプレイヤー個々の能力が高くても、その能力はチームの成果として活かされません。
チームの為に自分の能力を使うチームスポーツに対して、クライミングは自分が登るルートに自分の能力の全てを使います。つまりアプローチが違うのです。
スポーツチームから抜けた子がクライミングでグングン能力を伸ばしたという現象は、目標に一人で向かうのか、集団で向かうのかの違いによるもので、得意な分野が当てはまった結果なのです。
クライミングは運動神経に関わらず努力した時間の分だけ報われる
運動神経とは、バランス感覚や反応速度、判断力など「運動を補佐するもの」を指します。そして、運動には能力値というものがあり、これを「運動能力」と言います。
骨格や筋力、視力や聴力まで、運動を行うために備わっている能力そのものを指します。

時々耳にする「運動神経は遺伝するの?」という一般的な疑問はこの運動能力を指しているのでしょう。運動能力は遺伝しますが、運動神経は鍛えて伸ばすものです。
クライミング初級者ルートは、運動能力のみで十分楽しむことができます。中級者ルートになると運動神経があったほうが楽に登れるようになりますが、必ず必要というレベルではありません。
海外の高難度のルートを目指すクライマーや、大会に出場するような選手になってくると運動神経は必ず必要になってきます。
つまり、一般レベルでは運動神経に頼ったスキルの向上よりも、運動能力をコツコツ伸ばしていくスポーツなので、練習した分だけ確実に上達するという特徴があります。
球技のように関節に衝撃がかからず負担が少ない
テレビなどで見かけるホールドに飛びつく動作は、基本的に室内のインドアクライミングジムでのテクニックです。そして、そういったテクニックが多いのは上級者のルートです。

自然の岩では飛びつく動作は殆どありません。クライミングエリアの岩質にもよりますが、岩は必ずいつかは欠け、形を変えます。それが登っている最中に起きるのか、数百年後に起きるのか厳密に分かる人はいません。
なので、自然の岩場ではホールドの形状をよく吟味しながら安全性も確かめつつ登ります。ゆっくり確実に登っていく動作が、自然のクライミングには求められるのです。
何かを打つ、遠くに投げる、などの動作がクライミング中には現れず、どんなに力んだとしても動き自体がゆっくりとしたものなので、関節に優しいスポーツなのです。
環境適応能力が身につく
「試合で対戦する相手より『私』が強くなるために練習しよう」「チームのスタメンに選ばれるために『私』はもっと練習しよう」など、通常スポーツの世界では自分が主語になります。
そして、自分という主語を基軸にトレーニングを行い、レベルを上げていきます。

しかし、自然のクライミングにおいて主語を自分にしてしまう事は、時として思わぬ危険を招く事があります。
例えば、長いルートを登っていて急な悪天候に見舞われたとしましょう。降りなければ危険な時、過度の自信は「この程度なら大丈夫だ」「自分ならいける」と思い込みがちです。
そうして安全な選択をするチャンスを見逃します。怪我程度で済めば良いですが、遭難や、最悪の場合は帰れなくなるという時もあります。
「自分」という個人が自然の中で出来る事は限られています。だからこそ、自然環境に自分を同調させる必要があるのです。それは周りに流されることとは違います。
環境の中に存在する自分を知るのです。そういったことがクライミングの中で身につけば、社会生活に戻った後も多くの場面で役立ってくれるでしょう。