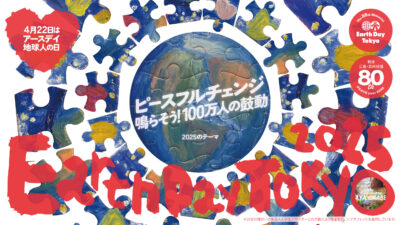3分の1ルールとは?

3分の1ルールとは、食品が製造された日から賞味期限までの期間を3等分し、以下の3つの期限をもうけたものです。
- 納品期限:最初の3分の1の期間に、納品しなければいけない。
- 販売期限:次の3分の1の期間に、小売店は店頭で販売してよい。
- 賞味期限:最後の3分の1の期間までは、消費者が食品をおいしく食べられるとする。
たとえば、製造日から賞味期限までの期間が6か月の食品があるとします。その場合、製造日から2か月を超えたものは、小売店に納品できません。納品できない食品のほとんどは廃棄されてしまいます。
こうした3分の1ルールは、とくに法律で定められているわけではありません。食品業界が自主的に行ってきた商習慣です。
海外にも同様の商習慣がありますが、アメリカは2分の1ルールで、ヨーロッパは3分の2ルールです。日本の3分の1ルールがいかに短いかおわかりでしょう。
3分の1ルールによる食品ロス問題の現状

日本国内の現状として、まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」は、年間570万トンです。なかでも3分の1ルールが主な原因といわれているのが、事業系の食品ロスで年間309万トン。3分の1ルールは食品ロスと密接に関わっているのです。
年間570万トンといえば、日本人1人あたりが毎日お茶わん一杯分のごはんを捨てていることになります。これは世界で飢餓に苦しむ人に向けた、食料援助量の約1.4倍に相当するものです。
こうした深刻な食品ロスの現状から、政府や企業によってさまざまな取り組みが進められていますよ。
出典:
農林水産省「食品ロスとは」
消費者庁「食品ロスについて知る・学ぶ」
私たちができる食品ロス削減への4つの取り組み

深刻な食品ロスの問題に対して、個人ができることはあるのでしょうか。私たちができる食品ロス削減への取り組み例を4つ挙げてご紹介します。
➀賞味期限にこだわらない
賞味期限とは「おいしく食べられる期限」のことです。消費期限の「安全に食べられる期限」のことではありません。
この賞味期限はほとんどが短く設定されています。なぜなら、出荷前まではきちんと温度管理などがされていても、出荷後の管理まではメーカー側が把握できないからです。
たとえば、店頭で直射日光に当たった場合なども考慮して、「おいしく食べられるか」を基準に賞味期限は決められています。つまり、賞味期限が近かったり、少し過ぎていたりする食品でも、すぐに食べられなくなるわけではありません。
賞味期限が近くても、積極的に購入すれば食品ロスの問題に貢献できます。具体的には、買い物をするときは棚の奥の商品ではなく、手前の商品から選んでいきましょう。
➁訳あり商品を通販サイトで安く買う

賞味期限切れ間近など、訳あり商品を販売している通販を利用することでも、食品ロス削減に貢献できます。賞味期限が間近なので、通常価格の半額以下になっている商品も。食品ロス削減と節約のどちらもできて、一石二鳥ですよ。
たとえば、以下のようなサイトをチェックしてみてください。
KURADASHI|食品ロス削減を目指す社会貢献型ショッピングサイト
食品ロス削減に取り組んでいる社会貢献型の通販サイトです。活動に賛同するメーカーから低価格で譲り受けた食品・食材・飲料・お酒などを、最大97%OFFで販売。また、売り上げの一部を環境保護団体などに寄付しています。
出典:KURADASHI
トクポチ|0円食品ありの会員制通販サイト
こちらも食品ロス削減をテーマにした食品通販のサイトです。取り扱っている商品の値段は、基本的には通常価格の60%スタート。その後、1週間ごとに割引率が10%ずつ追加されていくシステムです。最終的には価格0円になる商品もありますよ。
出典:トクポチ
③買いすぎない
食品ロス削減のための方法として、買いすぎないことも挙げられます。
買いすぎを避けるためには、買い物の前に冷蔵庫にある食品の量や種類などをチェックするのも方法です。冷蔵庫のなかを整理整頓して、なにがあるかすぐに把握できるようにしておくのもよいでしょう。
④冷凍保存できる食品は冷凍する
つい買いすぎてしまった場合は、冷凍保存できるものは冷凍するのがおすすめです。たとえば、エビを冷蔵保存した場合、保存できる期間はせいぜい2~3日。しかし、冷凍保存すれば2~3週間は保存できます。
食品ロス削減に向けた政府の取り組み

政府は食品ロス削減に向けて、どのような取り組みを行っているのでしょうか。具体的にご紹介します。
農林水産省
2012年に製造業・卸売業・小売業の話し合いの場として、「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」を設置。食品ロスはフードチェーン全体で解決すべき問題と考えました。
ワーキングチームの設置以降、メーカーに賞味期限を「年月日」表示から「年月」に変更するように促しています。また、納品期限も3分の1ルールを2分の1に緩和することに着手。大手スーパーやコンビニエンスストアが緩和に応じるようになりました。
出典:農林水産省「食品ロス・食品リサイクル」
消費者庁
消費者庁も食品ロス問題に対して、さまざまな取り組みを行っています。
3分の1ルールについては、2020年、農林水産省と連携して、玄米・精米の食品表示基準の改正を実施。米袋に表示されていた「調製年月日」と「精米年月日」を、「調整時期」「精米時期」に変更しました。
米袋に年月旬(上旬・中旬・下旬)を表示できるようにした結果、「精米した日付が古い」というだけで廃棄されていたお米を、削減できるようになったのです。
ほかにも農林水産省などと共に、令和3年11月~令和4年1月まで「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施。このキャンペーンでは外食時には残さず食べきることを普及させ、食品ロス削減を啓発しました。
また、食品ロス削減を消費者に普及させることを実施した者に、表彰する取り組みも行っています。
出典:消費者庁「食品ロス削減に向けた取組について」